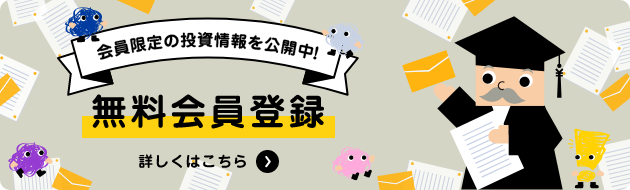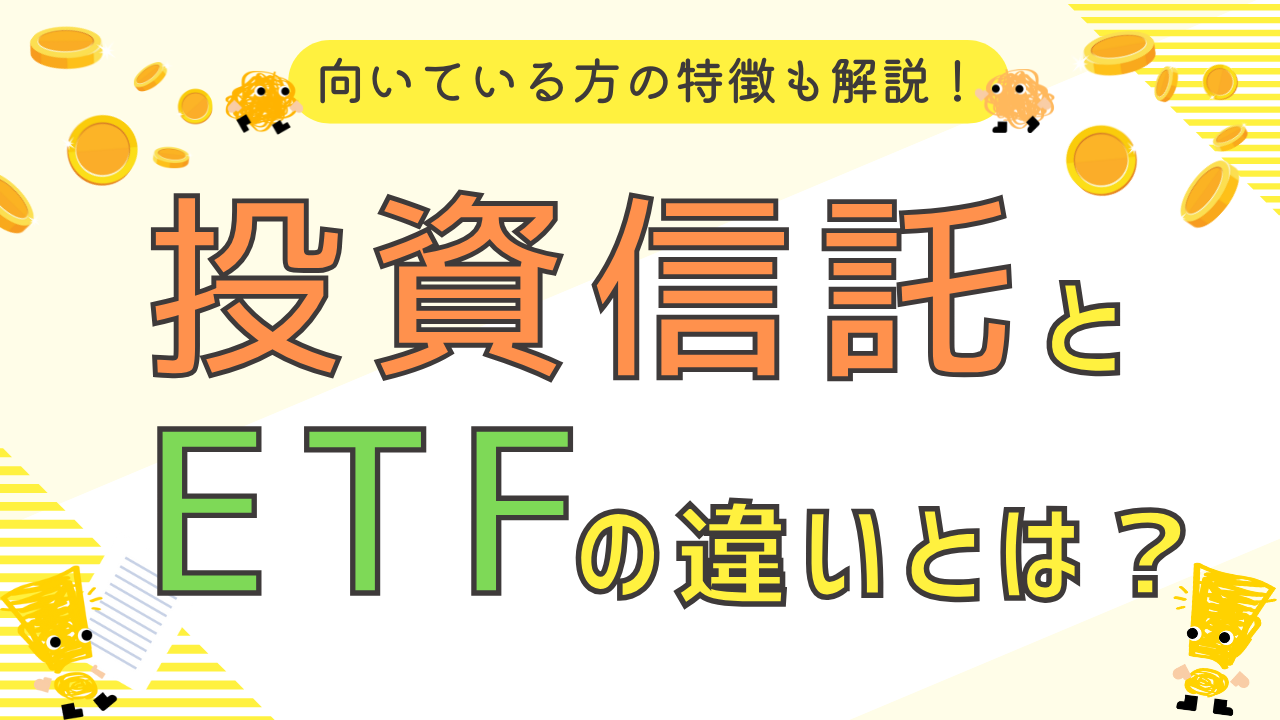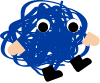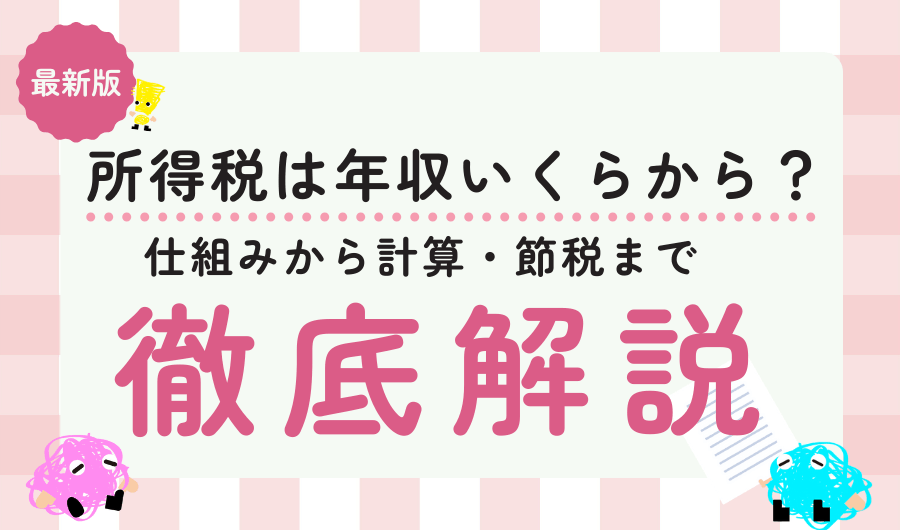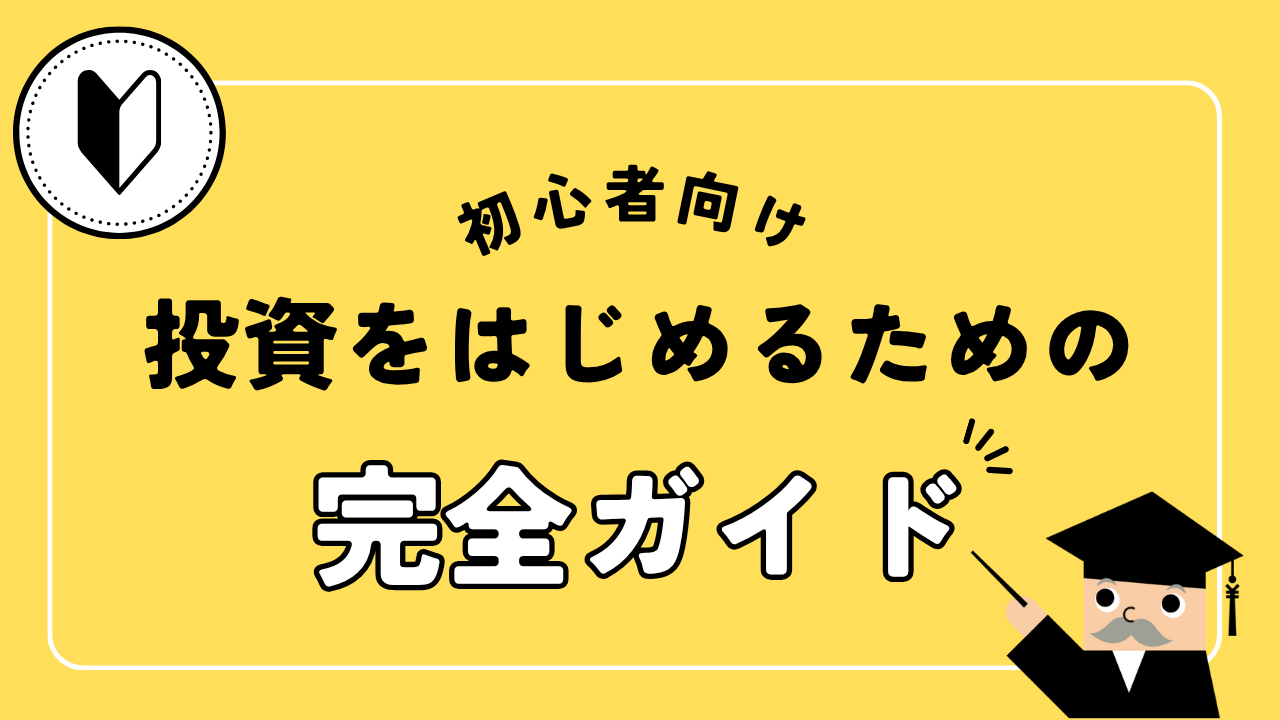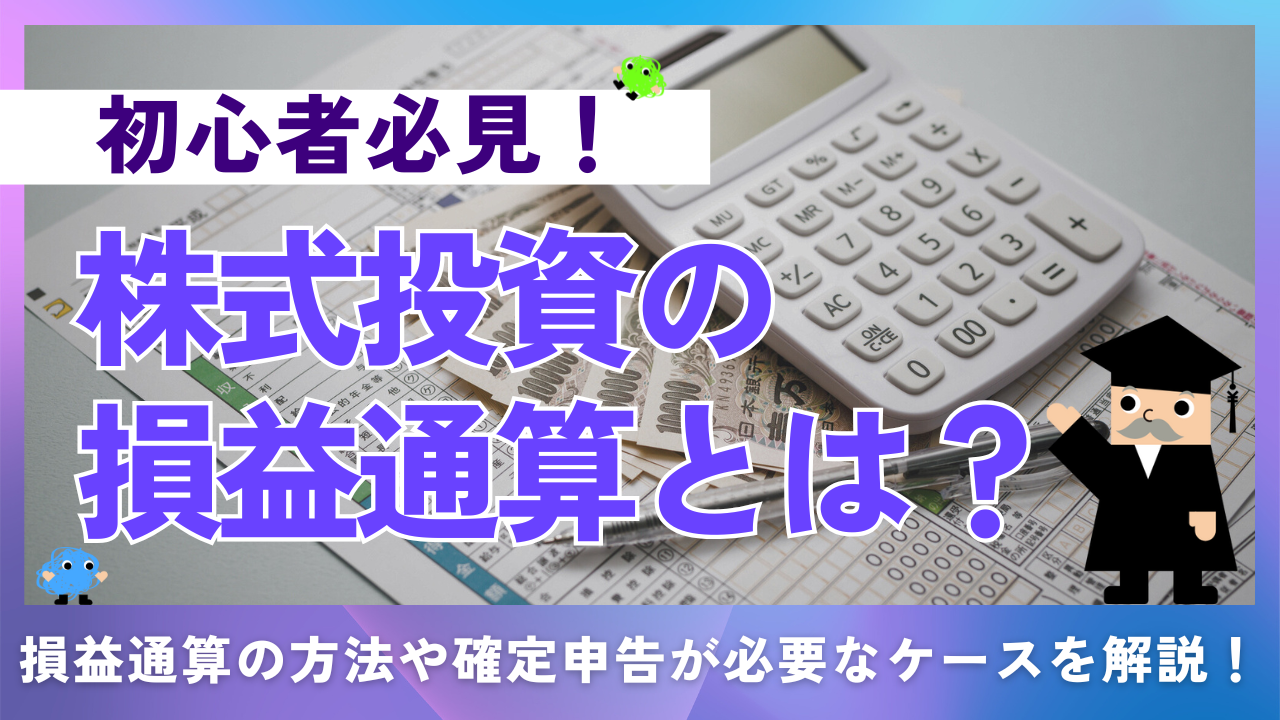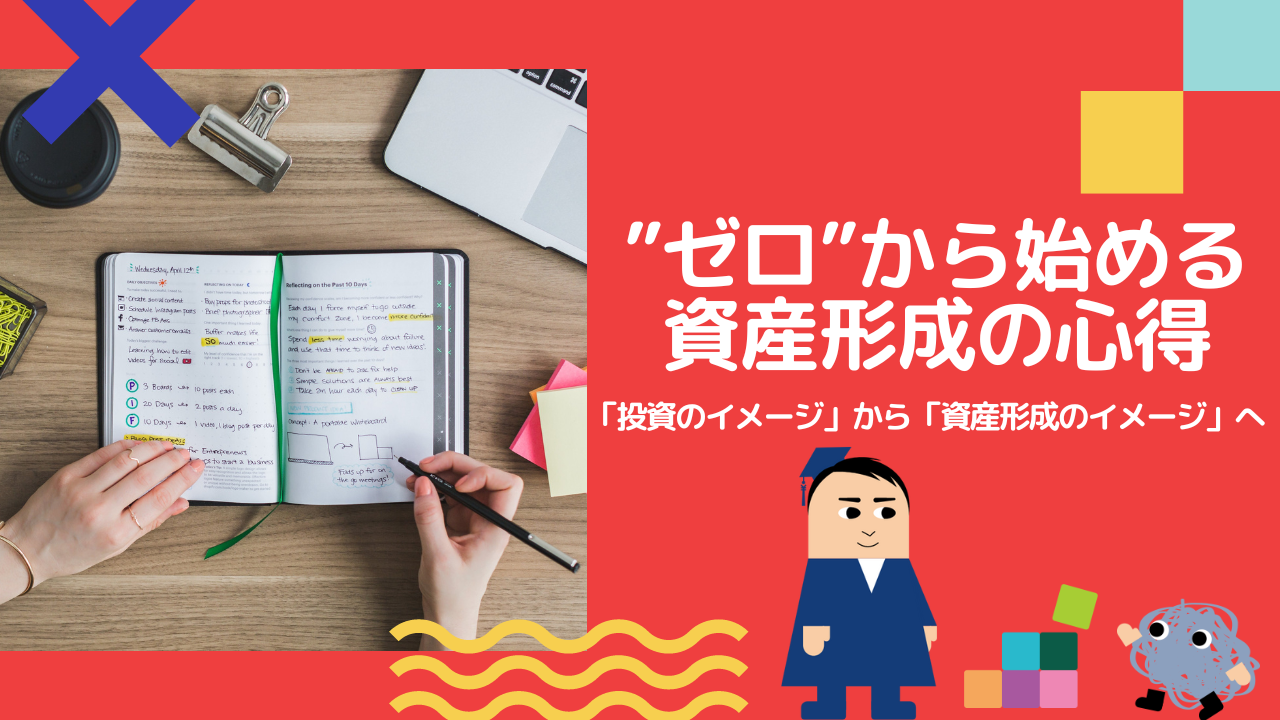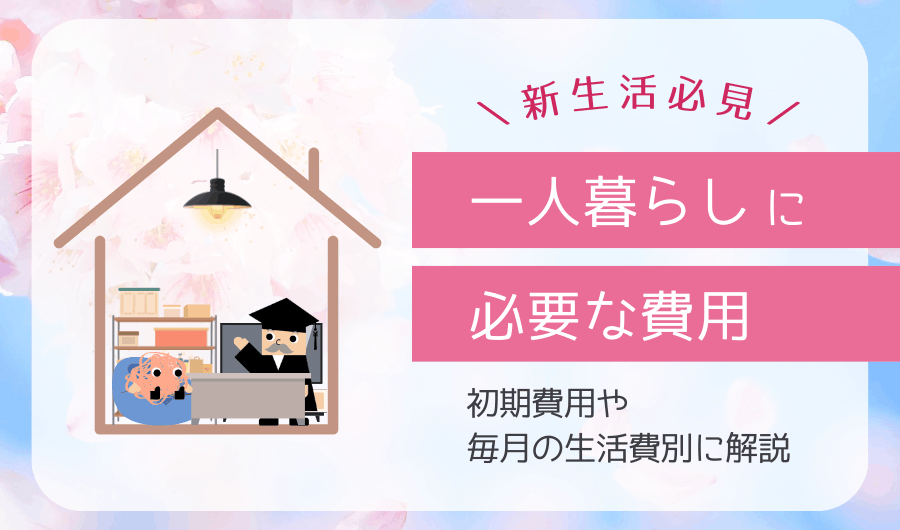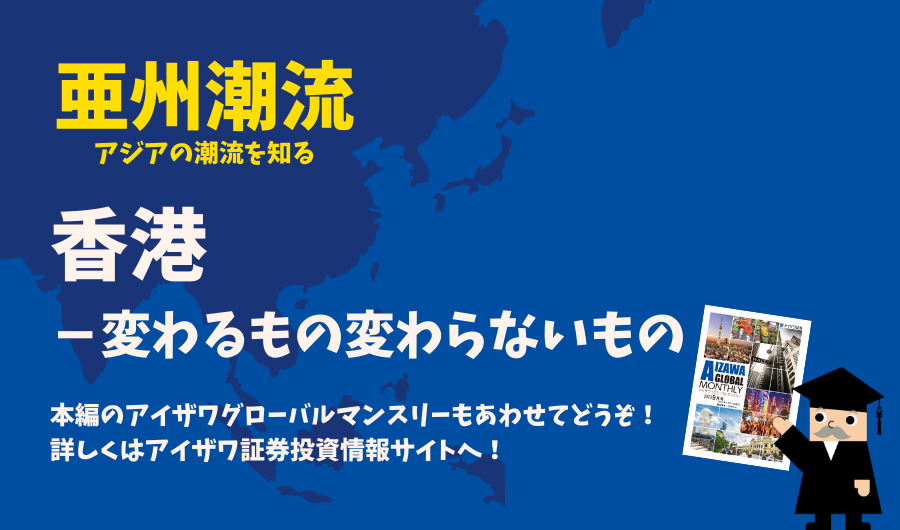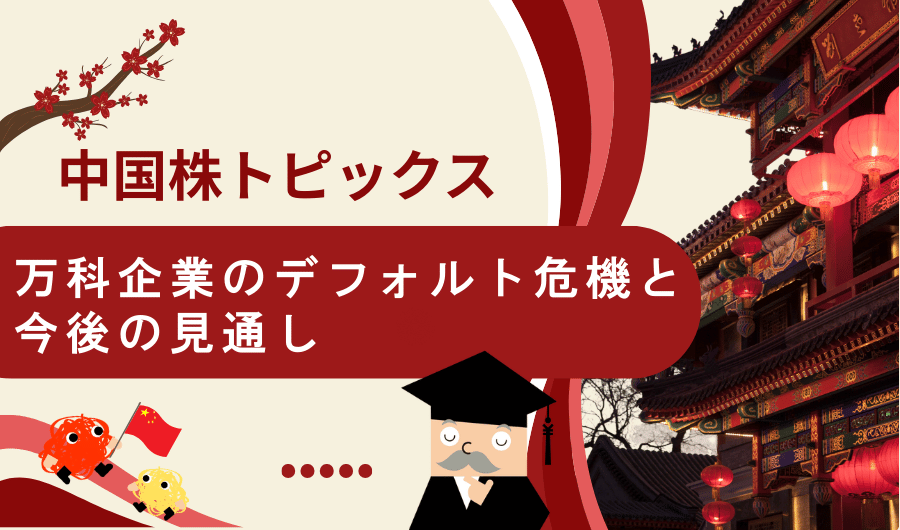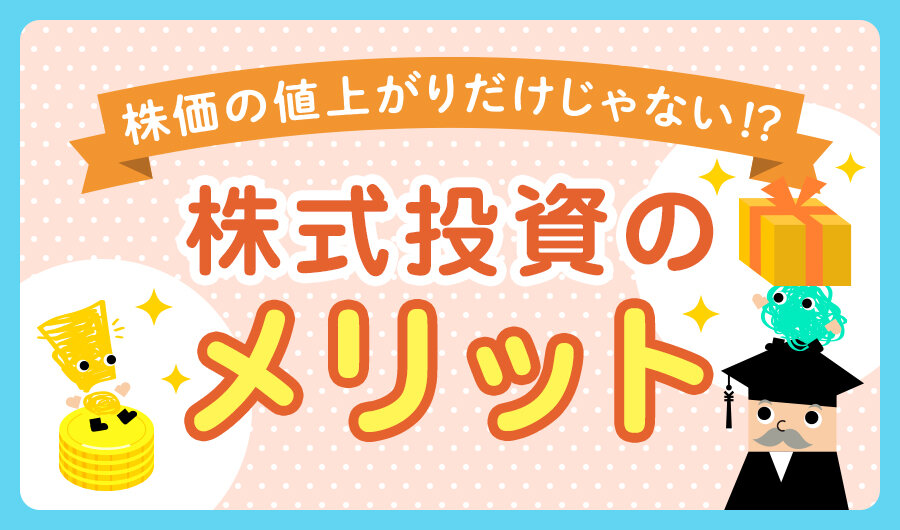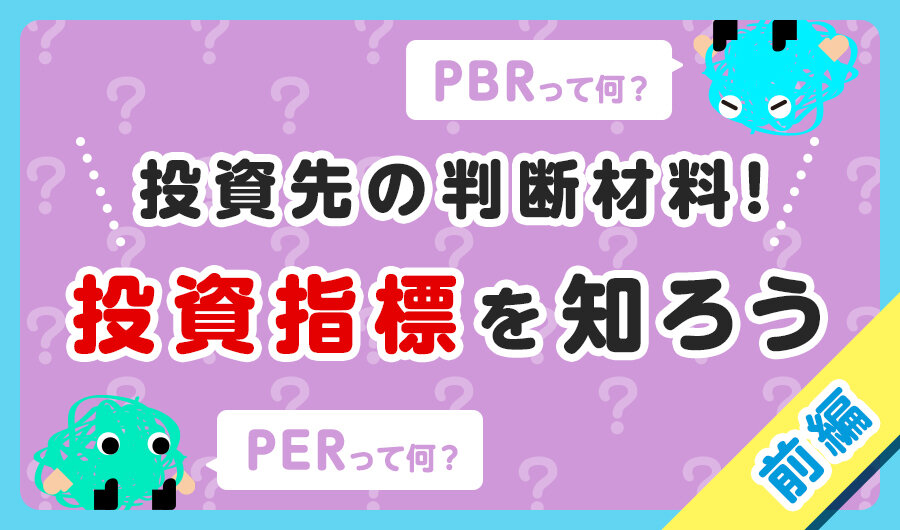【会社員向け】個人でできる税金対策・節税対策を紹介
2024.12.10 (火)
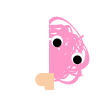
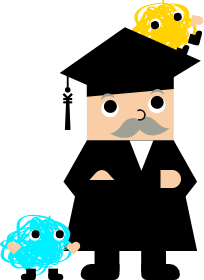


企業や個人事業主の中には、税金対策や節税対策をしている方が多くいます。一方、一般の会社員は給料から税金が天引きされていることが多いため、自分で節税できないと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし、実は会社員でも個人で税金対策や節税対策ができます。では、どのような対策ができるのでしょうか。今回は、会社員が個人で行う税金対策や節税対策について紹介します。
税金対策で知っておくべき「控除制度」とは?

節税や税金対策をする場合、まずは控除制度を知っておかなければなりません。ここでいう控除とは、給料から天引きされる所得税や保険料などを少なくすることです。天引きされる金額が少なくなれば、その分可処分所得を増やすことができます。
会社員は、控除制度を使って節税対策が可能です。控除制度を知って正しく活用することは、税金や保険料の個人負担額を減らし、手取り額を増やすことにつながります。
年末調整で利用できる控除

控除制度にはさまざまな種類があります。複数の控除制度を組み合わせることで節税効果を大きくすることが可能です。会社員が節税対策をする場合は、会社から提出を求められる年末調整の際に申告しなければならないものもあります。
ここでは、年末調整で利用できる控除について紹介します。
1.配偶者控除
配偶者控除は、所得税法上、控除対象となる配偶者がいる場合に控除される金額です。所得税法上控除対象となる配偶者は、内縁関係ではなく、民法上、婚姻関係を結んだ配偶者であり、納税者と生計が同じであることが求められます。
また、年間の所得金額が48万円以下(給与所得のみを得ている場合は給与収入が103万円以下)であり、その年を通して、青色申告者か白色申告者の専従者として収入を得ていないことも必要です。
上記の4点を満たした配偶者がいる場合は配偶者控除が可能です。例えば、パート勤めで年間収入が103万円以下である配偶者がいれば、控除対象となる可能性があります。控除金額は納税者本人の合計所得金額と、対象配偶者の年齢によって異なります。
2.扶養控除
扶養控除は、控除の対象となる子どもや親など親族を養っている場合に利用できる所得控除です。配偶者以外の親族や里子、市町村長から養護を委託された老人を養っており、生計を同じくしている場合は控除を受けられます。
扶養者の条件も年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみを得ている場合は給与収入が103万円以下)であり、その年を通して青色申告者と白色申告者の専従者ではないことが必要です。
一般の控除対象扶養親族(16歳~18歳)なら38万円、特定扶養親族(19歳~23歳未満)なら63万円、老人扶養親族(70歳以上)のうち同居老親等以外なら48万円、同居老親等なら58万円を控除できます。
※年齢はすべてその年12月31日現在を基準
また、令和5年分以後においては日本国内に1年以上の居住地を持たない「非居住者」である扶養親族については条件に適用していれば年齢に関わらず控除対象扶養親族となることがあります。
3.寡婦控除
寡婦控除(または寡夫控除)は、配偶者と死別か離婚したあと再婚をしておらず扶養親族がいる人が利用できる控除です。扶養親族の要件はなく、納税者の1年間の合計所得金額が500万円以下で、かつひとり親控除に該当しない場合は寡婦控除が受けられます。寡婦(夫)控除で控除できるのは27万円です。
この場合の「配偶者」は民法上の婚姻関係があった方を指し、内縁関係である場合は寡婦控除の対象外となります。
4.ひとり親控除
ひとり親控除は、現時点で婚姻をしていない方や配偶者の生死がわからない方が対象です。現在の婚姻によるので、過去に婚姻していたかどうかはどちらでも構いません。合計所得金額が500万円以下かつ、生計を同じくしている子どもがいる方が35万円の控除を受けられます。
生計を同じくしている子どもは総所得金額等が48万円以下であり、かつ他の方の親族となっていないことが条件です。
5.生命保険料・地震保険料控除
生命保険料控除と地震保険料控除は、控除の対象になる保険に入っている方が受けられます。婚姻や子どもなどは関係しないため、大半の会社員がこの控除を受けられ、その控除額は年間の支払保険料によって異なります。
生命保険料においては、2012年1月1日以降に加入した保険の場合は、年間に支払った額が80,000円を超えると一律で40,000円を控除できます。一方で、2011年12月13日以前に加入した保険の場合は、年間保険料が100,000円を超えると一律で50,000円が控除できます。
地震保険料の場合、年間の支払額が50,000円を超えると一律50,000円控除することが可能です。ただし、2006年(平成18年)12月31日までに契約を締結した従来の損害保険料に関しては、下記の要件を満たす場合、旧長期損害保険料控除の対象となります。
・2006年(平成18年)12月31日までに締結された契約であること
・満期返戻金などがあり、保険期間または共済期間が10年以上の契約であること
・2007年(平成19年)1月1日以後に、その損害保険契約などの変更をしていないこと
旧長期損害保険料の控除額については、年間の支払額が20,000円以上超えた場合、一律15,000円となります。
6.住宅ローン控除
住宅ローン控除は、マイホームの購入やリフォームなどを行った際に住宅ローンを使用した方が使える控除です。従来の控除期間は一般的に10年間でしたが、令和4年度の税制改正により、2022年1月1日~2025年12月31日までに新築住宅に入居した場合は入居してから最長で13年間控除を受けられるようになりました。
入居日が上記期間内の場合、年末時点における住宅ローン残高等の0.7%が所得税や住民税から控除でき、1年目は確定申告で還付金を受けなければならないものの、2年目からは年末調整で控除されます。銀行から秋ごろに届く残高証明書を大切に保管しておきましょう。
7.特定支出控除
特定支出控除は、給与所得のある方が仕事をする上で必要経費(支出)の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に控除を受けられる可能性があります。特定支出控除に該当するのは、下記の費目です。
・通勤費:通勤のための費用
・職務上の旅費:出張のための費用
・転居費:転勤にともなう引っ越し費用
・研修費:仕事で使う技術や知識の研修費用
・資格取得費:仕事に必要な資格取得の費用
・帰宅旅費:単身赴任先と自宅を往復するための費用
・勤務必要経費:仕事で必要な書籍や衣服、交際費など(上限65万円)
上記を控除するには職場の証明書が必要です。仕事にかかる経費が多い方は職場に相談して証明書を作成してもらう必要があります。
個人でできる節税対策

年末調整で控除を受ける以外にも、確定申告などを使って個人で節税できることもあります。ここでは、年末調整以外で個人ができる節税対策を紹介します。
1.医療控除
納税者本人と配偶者や子どもなど、生計を同じくしている家族の医療費の合計が10万円を超える場合は、医療費控除が受けられます。
ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%が控除額として計算されるため、医療費が10万円未満でも控除が適用される場合があります。
また、セルフメディケーション税制という制度もあります。これは自身や生計を同じくしている親族が医薬品などを購入した際に、その金額に応じて所得から控除できる制度です。
どちらか一方の制度しか使えないため、医療費が10万円を超えない場合にセルフメディケーション税制を使う方法もあります。
2.ふるさと納税
ふるさと納税も会社員の節税対策として定番化しています。ふるさと納税をすると寄附金控除が受けられるので、毎年12月ごろになると駆け込みでふるさと納税をする方も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税は、選んだ自治体に寄付した金額から2,000円を差し引いた残額は寄附金とみなされ、翌年の所得税や住民税から控除される制度です。
翌年納付すべき税金を前払いする仕組みであり、実際に払う金額が減るわけではないため、節税とはいえないかもしれませんが、返礼品がもらえることでお得感があります。
詳しく知りたい方はこちら(ふるさと納税のメリットとは?注意点や始め方も解説 | ゼロから学べるアイザワ投資大学)
3.NISA
NISAは少額投資非課税制度のことです。NISA口座を使った投資で得た運用益が非課税になるのが特徴です。投資額に上限はありますが、非課税の期間が無期限になるため、NISAで運用をして得た利益はそのまま収入となります。間接的に節税対策として活用している方も増えています。
4.iDeCo
iDeCoは、個人型確定拠出年金のことで、私的年金制度のひとつです。将来的に政府からもらえる公的年金のほかに、老後の自分のために掛けておくお金です。掛金は全額控除され、運用益も非課税となります。
老後にお金を引き出す場合は、掛金とその運用益の合計額をもとに年金として受け取ることができます。老後のための貯蓄を考えている方は、今から節税対策をしながら貯め始めるのもおすすめです。
5.株取引に関する控除
株取引をしている方でもし損失が出てしまった場合、確定申告をすれば結果的に課税されない可能性もあります。株取引で出た損失を確定申告によって、他の取引で出た利益や配当と相殺すれば、その分を所得から控除できます。
損失は3年間繰り越せるため、株取引をしている方は利益だけでなく損失にも注目して控除できないかどうか確認しましょう。
まとめ
節税対策は、事業主だけでなく、会社員も活用できます。適切な手続きを行えば、複数の節税メリットを受けることが可能です。年末調整や確定申告などを通して節税できるため、使える制度がないか確認してみましょう。
ご留意事項
免責事項
本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。