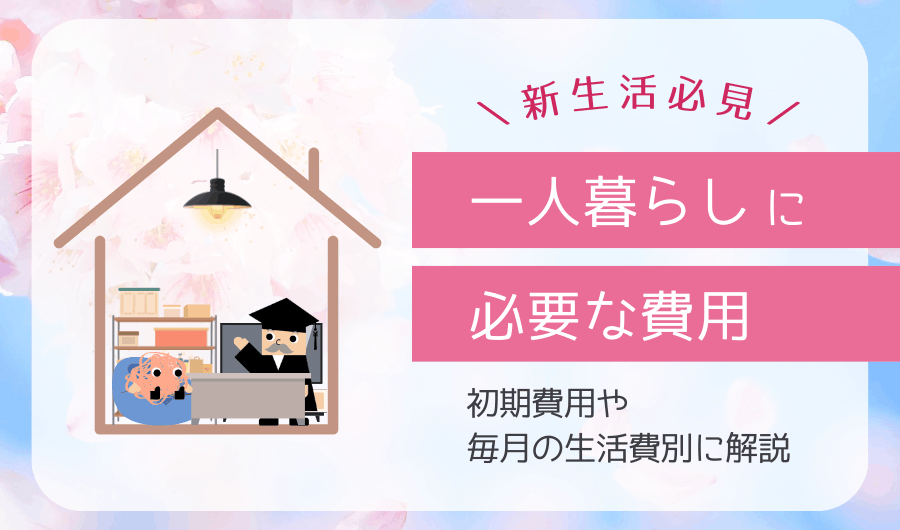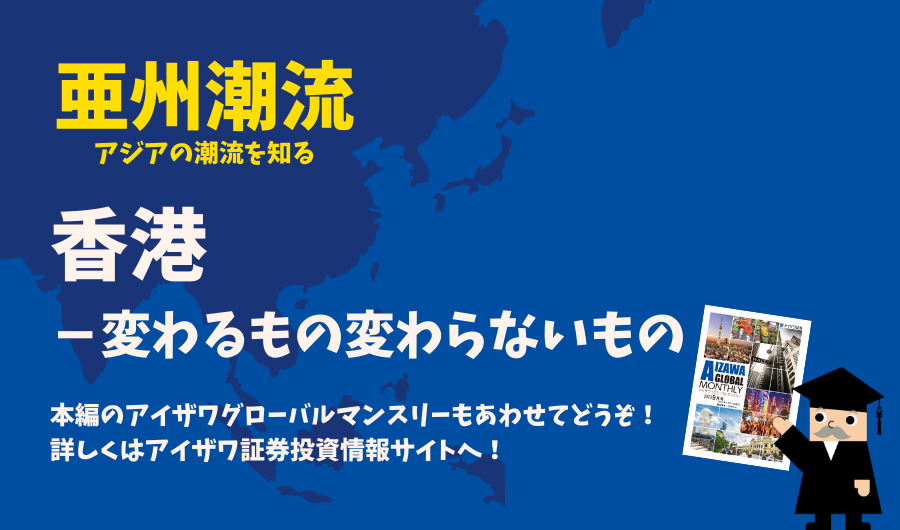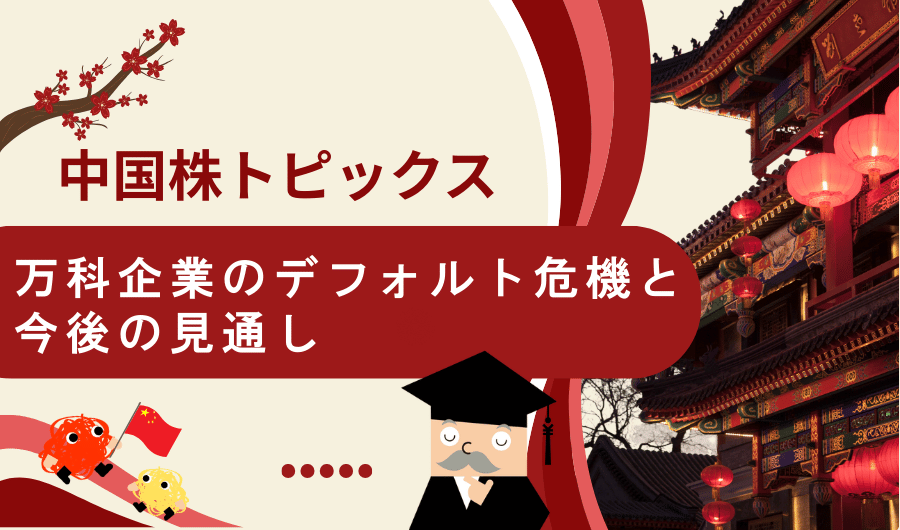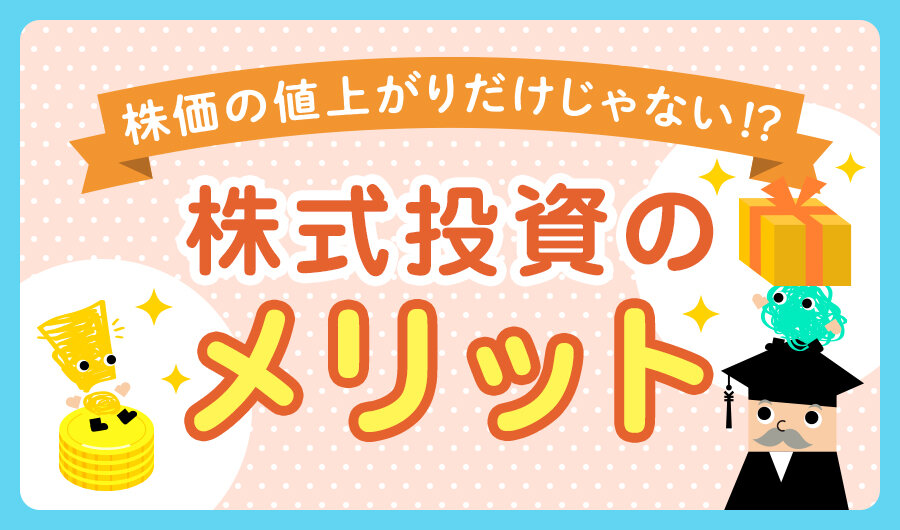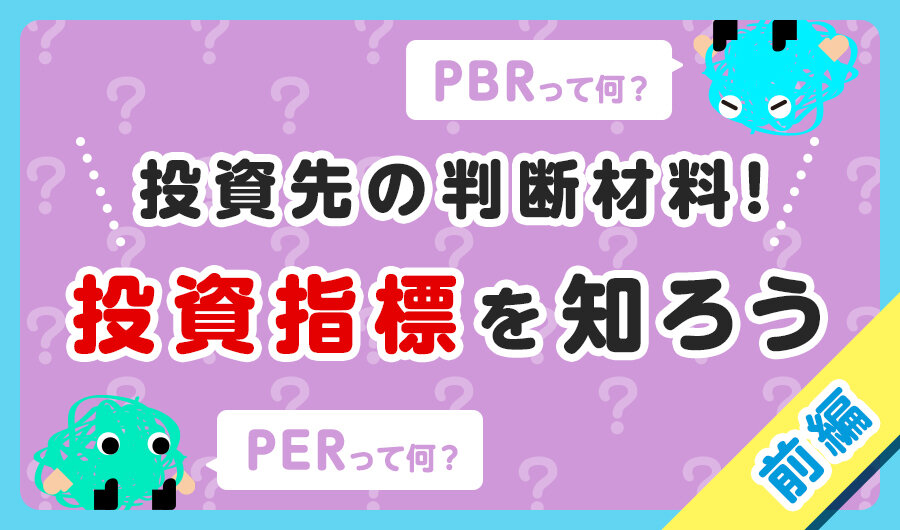円安と円高、どっちがいい?企業や生活、外貨建て資産への影響を解説
2024.12.11 (水)
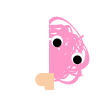
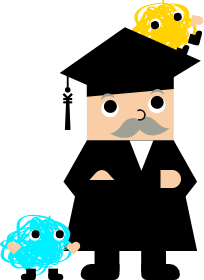

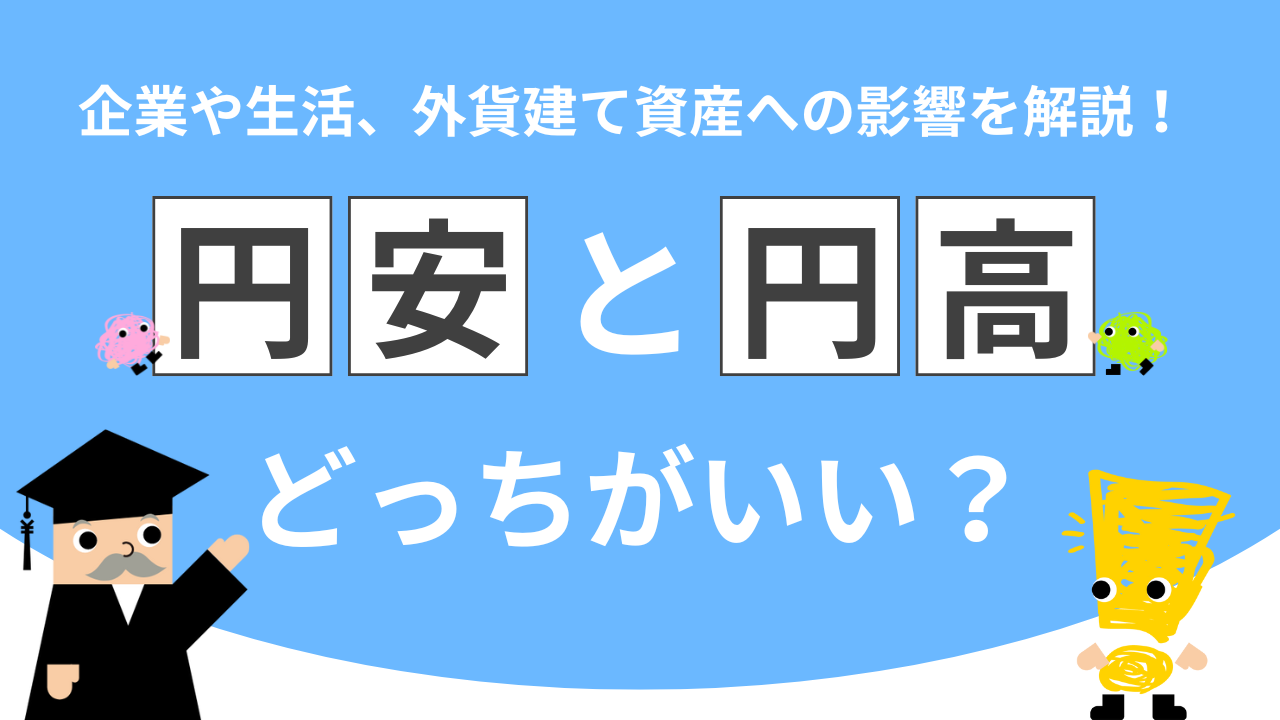
「円高と円安、一体どちらが良いのだろう」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。円高・円安はそれぞれメリット・デメリットがありますが、具体的にどのような影響をもたらすのか、よく理解していない方もいるかもしれません。
今回は円高と円安の特徴や、それぞれがもたらすメリットとデメリットについて解説します。
そもそも円高・円安とは

円を含む「通貨」の価値は、単体そのものでなく、他のモノとの比較や経済状況によって常に変動します。また、円の価値が他の通貨に対して高いか低いかで、経済は大きく左右されます。ここでは、円高と円安についての特徴を紹介します。
円高とは
円高とはグローバルな経済活動の中で、日本円が他の国の通貨(ドル、ユーロなど)に対して価値が高くなる状態のことです。ドル安を背景に円高が進んでいる状況を例にあげると、100円出すと1ドル得られたのが、100円で以前の倍のドル(2ドル)を手に入れることができる状況となります。
円高が進んだことで日本円を多くのドルと両替できるため、日本円の実質的な購買力が海外で向上したことを示します。
円安とは
一方、円安とは簡潔にいうと日本円が他の国の通貨よりも価値が下がることです。「昔は1ドルで100円分のモノが買えたのに、今は200円払わないと買えなくなった」という状況は、まさに円安が進んでいる状態といえます。
円安になると、同じものを買おうとしても以前の倍の日本円が必要になります。
円高・円安の覚え方
円高や円安などの経済用語は、日常会話であまり使わないため、どちらの意味かわからなくなることもあるかもしれません。
そのようなときは、1ドルに対して円がどのように変化するかを考えることが大切です。この仕組みを複雑に感じてしまう方は、下記のように覚えるのがおすすめです。
・1ドルで買える円が少ない状態=円高
・1ドルで買える円が多い状態=円安
例えば、今まで「1ドル=100円」で購入できていたものが「1ドル=50円」になっている場合は円高です。一方、「1ドル=200円」になっている場合は円安となります。
円高になるとどうなる?

円高になると、私たちの暮らしや経済活動にさまざまな影響がみられます。ここでは、主に「国内企業への影響」「私たちの生活への影響」「外貨預金への影響」の3つの視点から、円高がもたらす変化について解説します。
国内企業への影響
円高になると、輸入品を扱う企業に有利に働きます。100ドル分(100個)の輸入品を仕入れる場合を例に考えてみましょう。
【1ドル100円の場合】
・100円×100個=10,000円
【1ドル80円の場合】
・80円×100個=8,000円
このように、円高になると1ドルあたりの円が少なくなり、仕入れ額が8,000円となることで支出を2割削減できます。
その結果、企業の利益が増えやすくなり、業績が向上して結果として株価が上昇する傾向があります。また、円高になるとより多くの外貨を取得できるため、日本円での海外不動産の取得や、企業の買収も容易になるでしょう。
生活への影響
円高になると、海外からの輸入品が安くなるため、私たちの生活にさまざまな恩恵がもたらされます。日本は多くの食料品や資源を海外から輸入しています。そのため、円高の進行で商品をより安く購入できるようになり、家計の負担が軽減されるでしょう。
また、海外旅行を計画している方にとって、円高はお得に旅行を楽しめるチャンスです。同じ日本円で、より多くの現地通貨と交換できるため、海外での滞在費を抑えたり、観光やショッピングを楽しんだりすることができます。
外貨預金への影響
為替レートは常に変動しているため、外貨預金を円に戻すタイミングによって損益が大きく変化します。そもそも為替差損は、外貨預金で預けている通貨の価値が円に対して下がってしまったときに起こります。
例えば、「1ドル=100円」で100ドル預けていた場合、円高で95円になると100ドルを円に戻したときに9,500円しか受け取れません。つまり、預けていたときよりも500円損してしまうのです。
円安になるとどうなる?

円安になった場合は、経済や私たちの生活にどのような影響を及ぼすのでしょうか。ここでは、円高の場合と同様に、「国内企業への影響」「私たちの生活への影響」「外貨預金への影響」の3つにわけて解説します。
国内企業への影響
一般的に円安は輸出企業にとって、有利な状況をもたらします。例えば、1ドル100円のときに商品を100個販売したときと、円安で1ドル120円になったときの場合を比較してみましょう。
【1ドル100円の場合】
・100円×100個=10,000円
【1ドル120円の場合】
・120円×100個=12,000円
同じ商品を販売しても、1ドル120円の場合は円換算での売上が2,000円増加するため、企業はより多くの利益を得られます。
生活への影響
円安は、輸入品価格の上昇や海外旅行の費用増加などを引き起こし、私たちの生活水準を低下させるおそれがあります。特に、エネルギーや食料品など、輸入に頼っている生活必需品の価格上昇は、家計に対して大きな負担をもたらします。
さらに、為替レートが円安に動くと、気軽に海外旅行へ出かけることが難しくなるかもしれません。
外貨預金への影響
外貨預金は為替レートの上昇によって、為替差益が生じる可能性がありますが、下落すれば損失が出るリスクもあります。
例えば、円安で「1ドル=100円」のときに外貨預金を預け入れ、「1ドル=120円」のタイミングで円に両替して引き出すと、1ドルあたり20円の為替差益が得られます。外国株や外債においても同様に、為替損益が発生する仕組みです。
円高、円安どちらが良いかは立場によって異なる
先述の通り、円高・円安の特徴や影響について紹介しましたが、それぞれの立場や状況によってメリットやデメリットは異なります。
ここでは、消費者側の視点から円安によって、どのような影響がみられるのか詳しく解説します。
国内消費者が影響を受けるのは円安
消費者目線で考えると、円安は家計の支出を増やし、生活を圧迫する要因となります。日本は輸入品に頼っているものが多く、円安になると日々の生活で使う生活必需品の値段が上昇し、家計の負担が大きくなってしまうのです。
2022年から続く物価上昇により、家計の支出はますます増えています。値上げラッシュの原因として、新型コロナウイルスからの深刻な人手不足や、ロシアによるウクライナ侵攻、地球温暖化による異常気象などが考えられます。
ほかにも、2022年に発生した米ドル高円安も原因のひとつです。給料は横ばいのまま、生活費だけが上がってしまうと、消費者の生活は今後も苦しくなるのかもしれません。
円安対策として外貨の金融資産を保有する方法がある
円安による物価上昇が続く現在、円預金だけでは資産を十分に守れない可能性があります。物価の上昇が続くなか、資産を増やしたいと考えている方は、外貨預金や米国株式、米国株式を対象とした投資信託といった資産運用に目を向けてみるのもひとつの方法です。
ただし、外貨預金や株式投資は為替変動や市場の動きによって利益がでることもあれば、損失を出す場合もあります。事前にしっかりとリスクについて理解した上で、自分に合った資産運用方法を選択することが大切です。
まとめ
円高と円安、どちらが良いのかの問いに対しては立場や状況によって変わるため、一概に良し悪しを決めることはできません。
円高になると、輸入企業の追い風となり、消費者にとっては輸入品が安く手に入ることから、家計の負担が軽減できます。
一方で、円安が進めば輸出企業の業績を後押しする効果が期待できますが、輸入価格の高騰や海外旅行の費用増加につながります。円高・円安は、それぞれにメリットやデメリットがあるため、状況に応じて必要な対策を講じましょう。
ご留意事項
免責事項
本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。

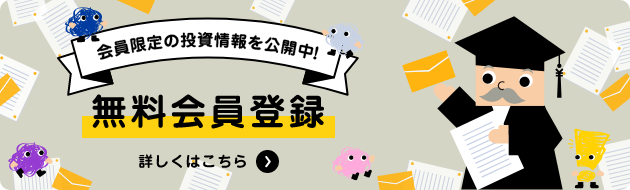

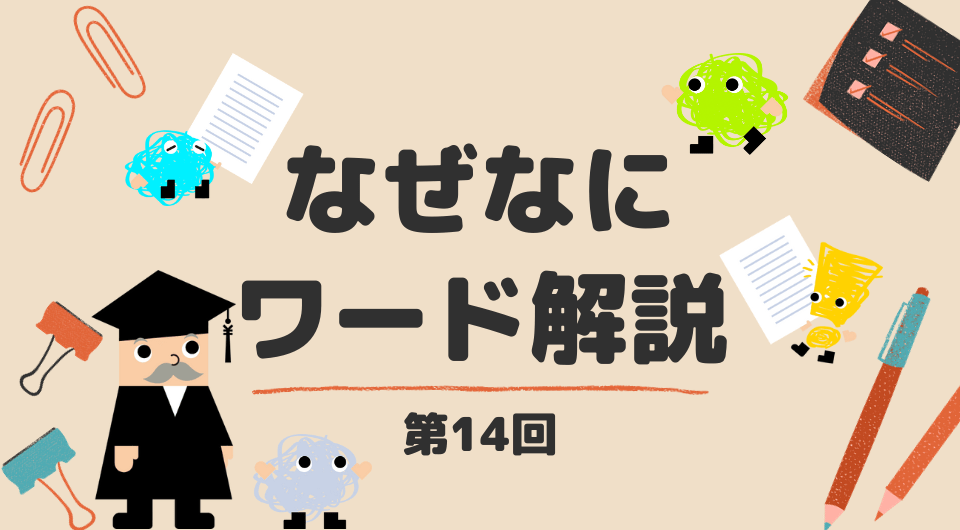

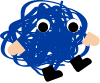

![マンガで分かる金融知識 ~正しい金融商品の選び方~ 第7話 「安い]だけで選択していませんか?](../assets_c/2022/01/e5969e00b7b1c2d73863c85067dc0c8150a7bd2c-thumb-960x530-1423.png)