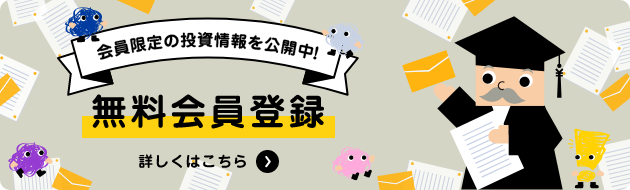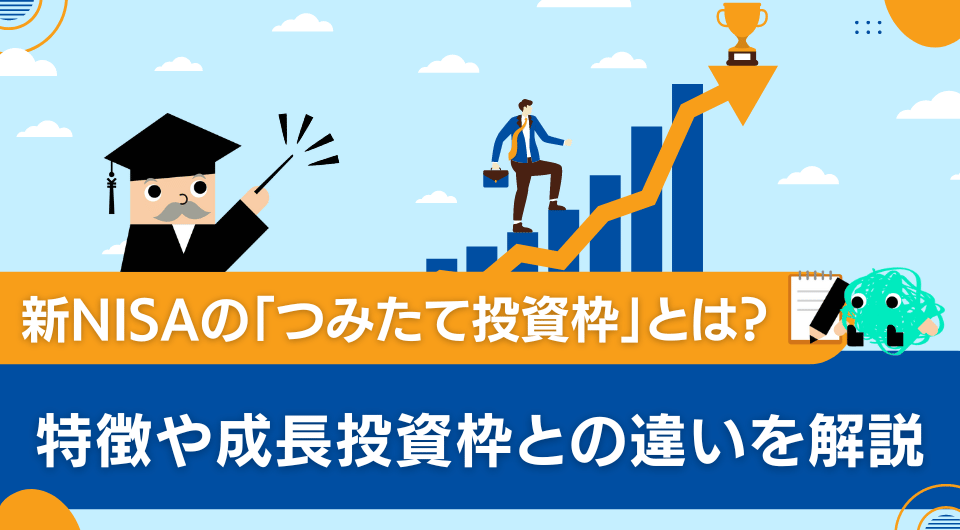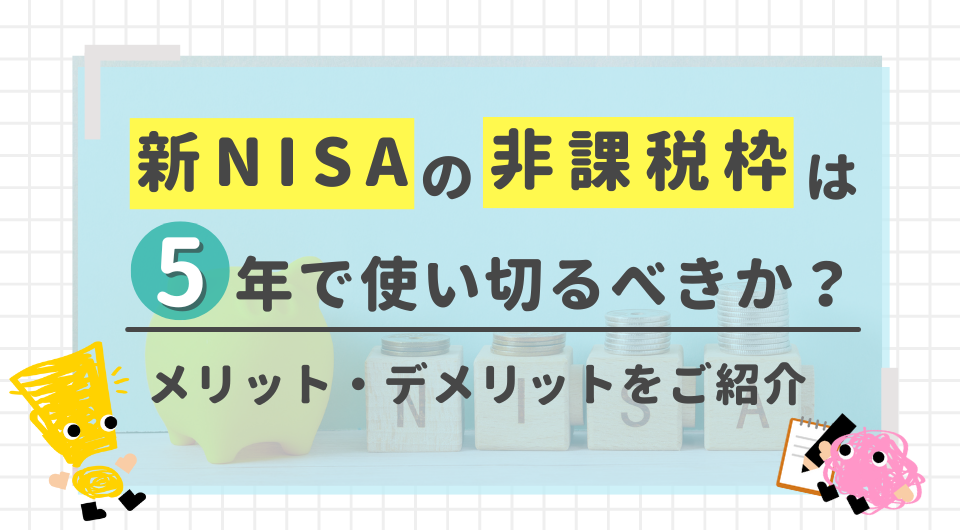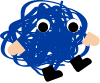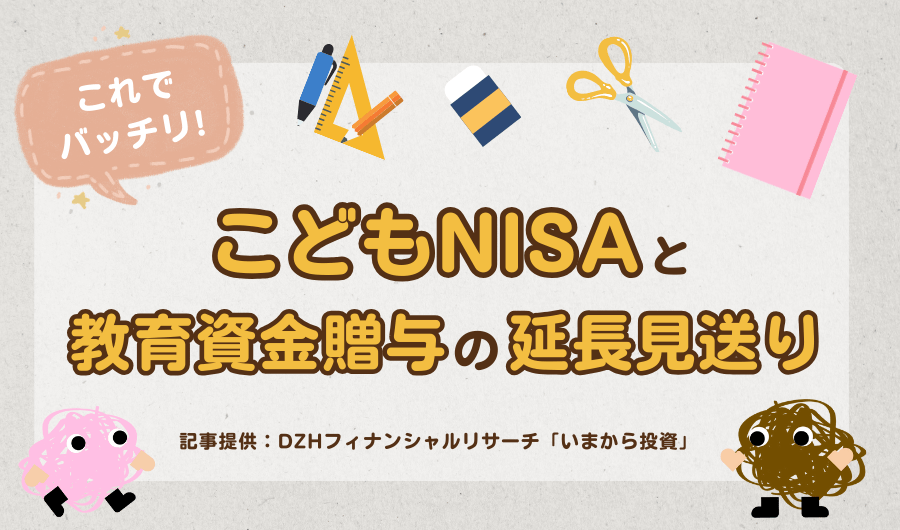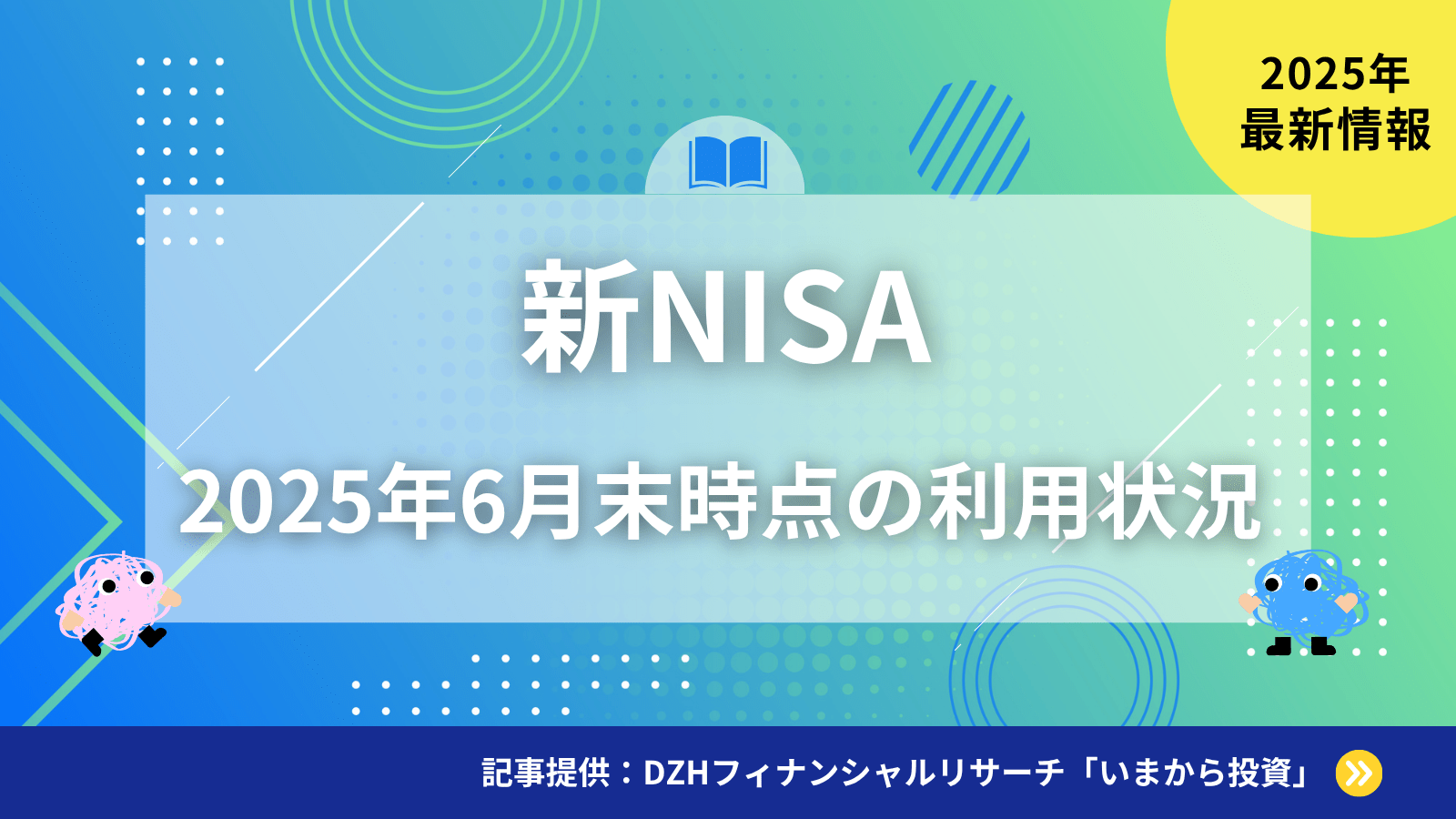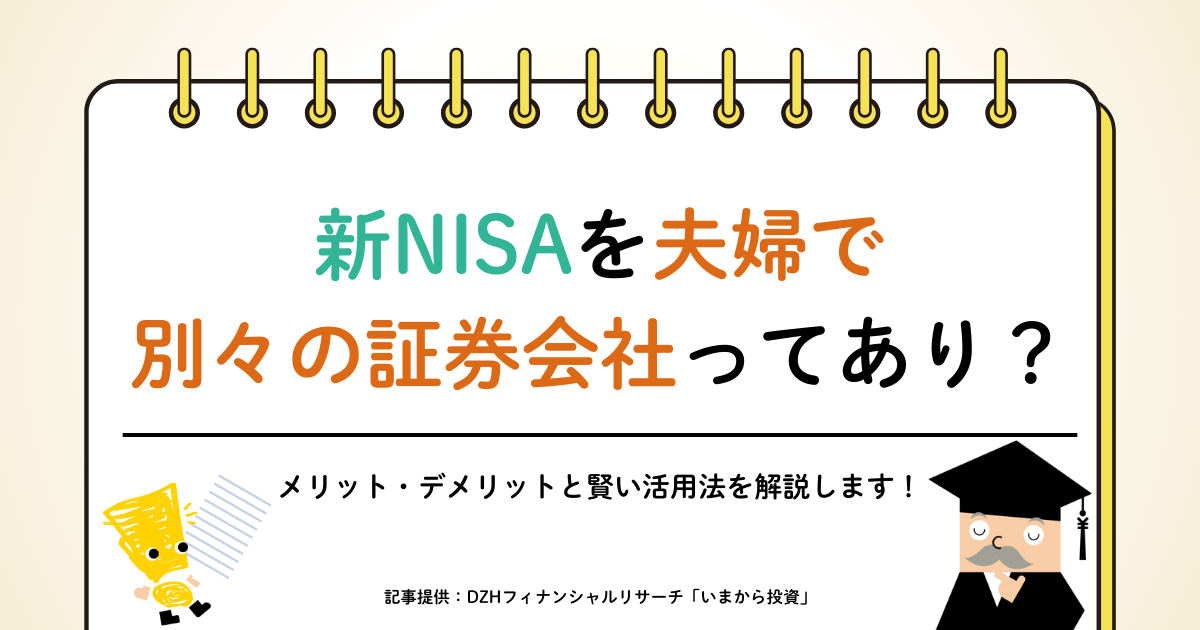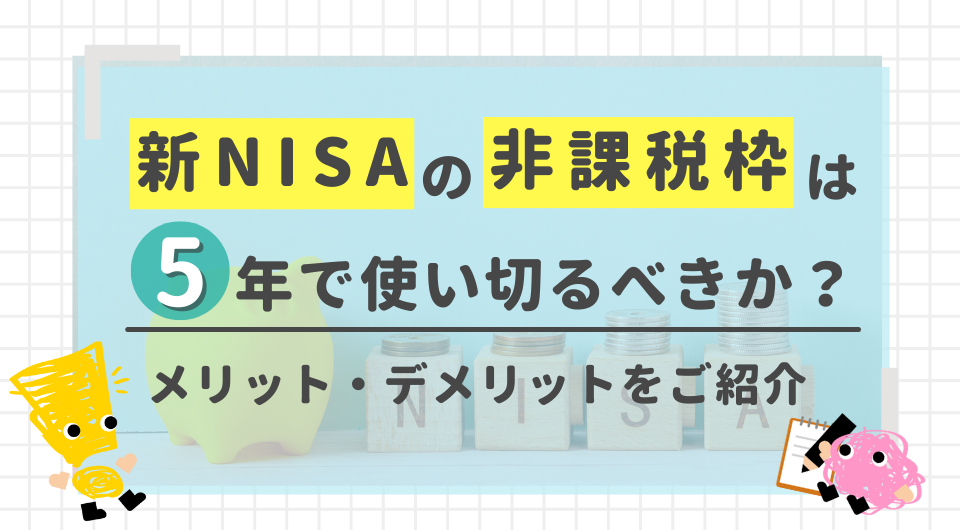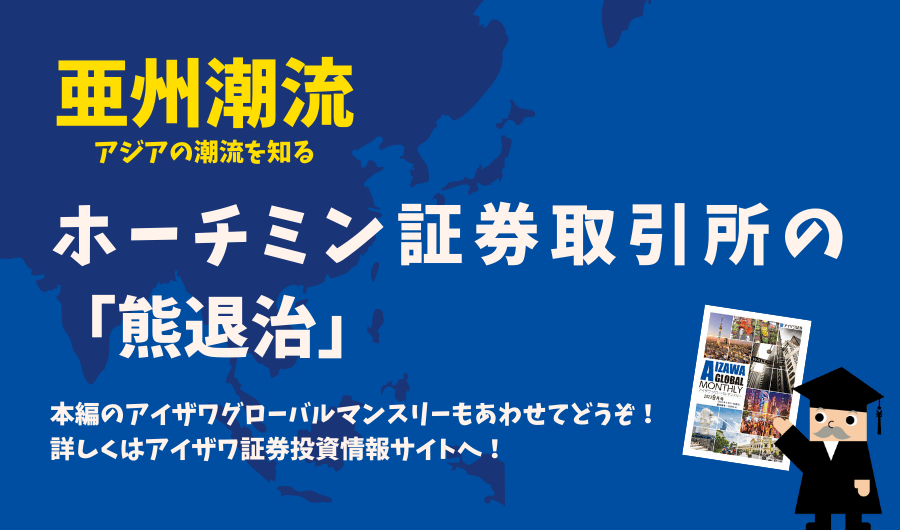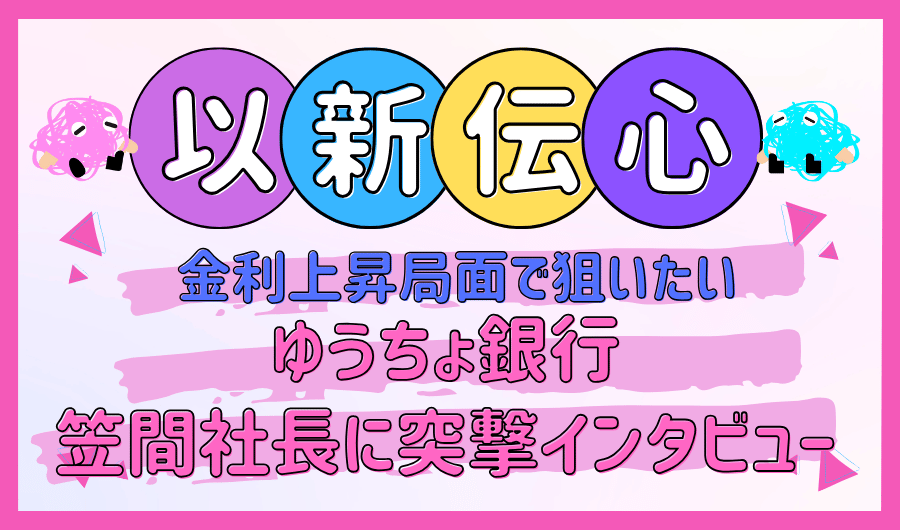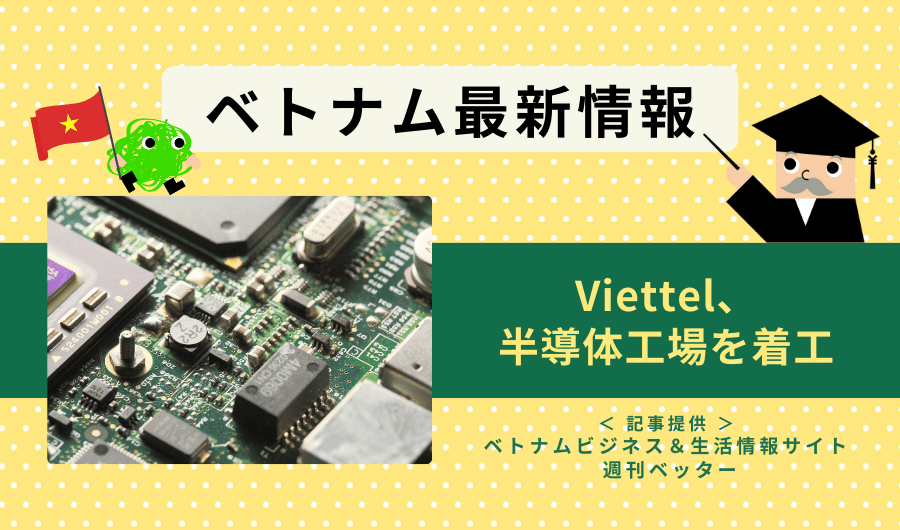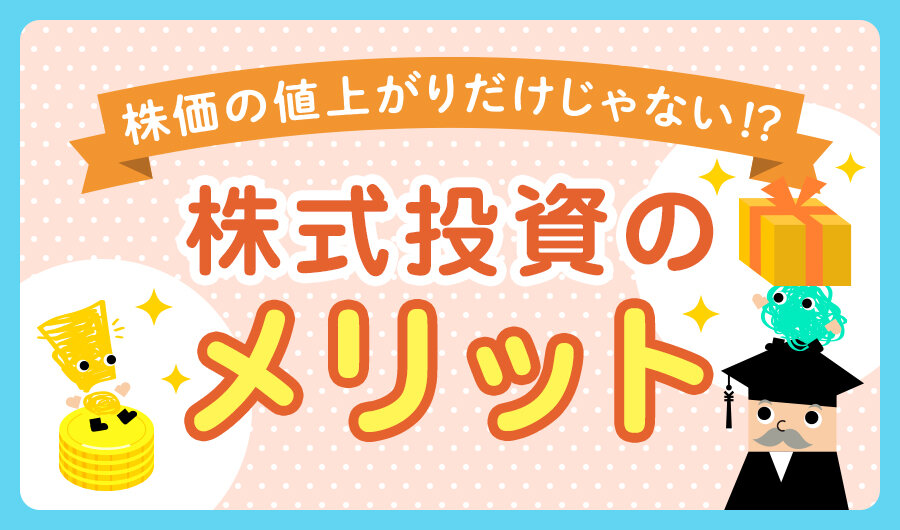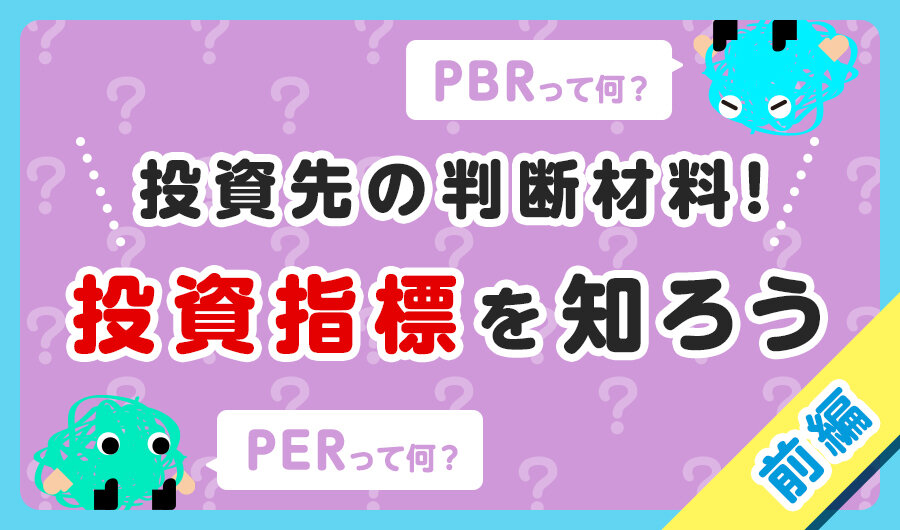成長投資枠とつみたて投資枠で同じ銘柄を買う?メリットとデメリットを解説
2025.02.20 (木)
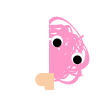
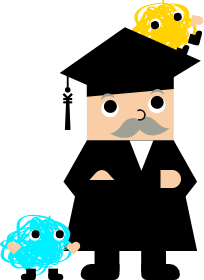

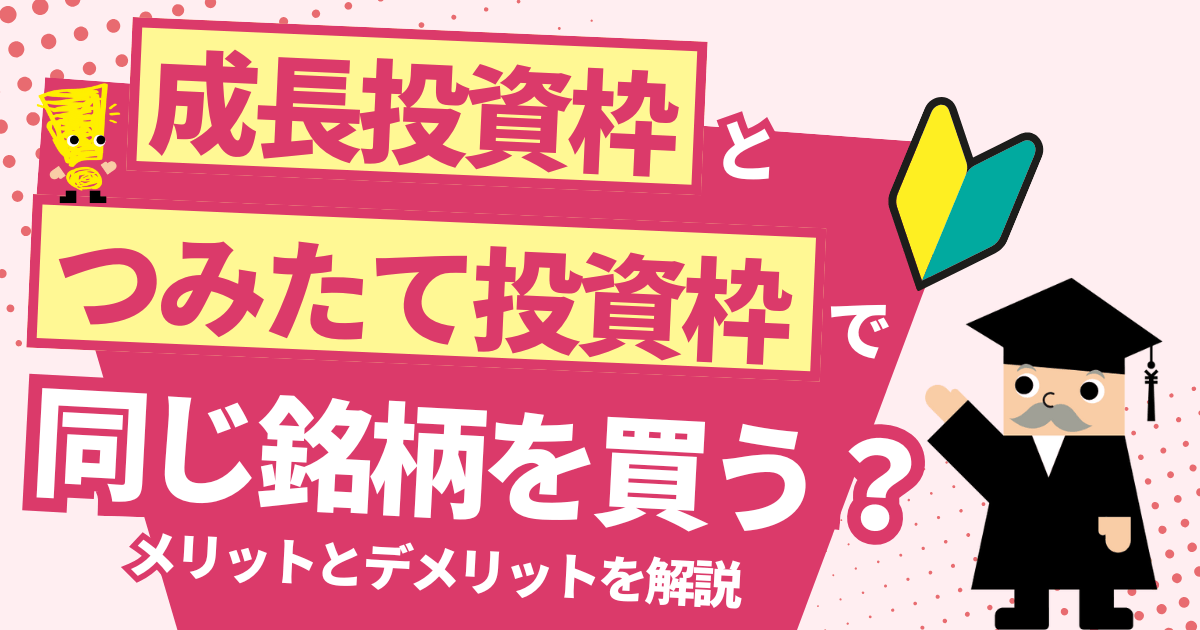
2024年から始まった新NISAは、成長投資枠とつみたて投資枠に分かれています。対象商品は一部異なりますが、両方の枠で買える銘柄もあるため、同じ銘柄を買おうと検討している方もいるかもしれません。
今回は、NISAの成長投資枠とつみたて投資枠で同じ銘柄を買う場合のメリットとデメリットを解説します。
成長投資枠とつみたて投資枠の違い

NISAは少額投資非課税制度のことで以前からもありましたが、2024年に内容が一新されました。一般口座や特定口座と異なり、NISA口座を利用して得た利益は非課税として扱われます。
NISAは成長投資枠とつみたて投資枠に分かれていますが、両者の違いを簡単に表すと次の表の通りです。

では、両者の違いを詳しくみていきましょう。
年間投資可能額
年間投資可能額は成長投資枠では240万円、つみたて投資枠では120万円が上限です。1月1日から12月31日までを一つの期間として区切り、カウントされます。年の途中でNISA口座を開設した場合も同様です。
両方の枠をあわせると年間360万円のため、まとまった金額の投資ができます。
生涯非課税限度額
生涯非課税限度額は、成長投資枠とつみたて投資枠を合計して1,800万円です。このうち成長投資枠には1,200万円までという上限が設けられています。
成長投資枠を上限まで使っている場合には、つみたて投資枠は600万円です。つみたて投資枠のみで投資する場合は、1,800万円までが非課税枠になります。
投資対象商品
成長投資枠の投資対象商品は、上場株式・ETF・投資信託・REITです。ただし、高レバレッジ商品や毎月分配型など一部の投資信託は除外されています。
つみたて投資枠は金融庁が設けた基準を満たしている投資信託が対象です。長期・分散投資に適している投資信託だけがつみたて投資枠で購入できます。
また各枠の取扱銘柄は金融機関ごとに異なるので、事前に自身が買いたい銘柄が買えるのか確認しましょう。
成長投資枠とつみたて投資枠を同じ銘柄にするメリット・デメリット

成長投資枠とつみたて投資枠で同じ銘柄に投資する場合のメリットとデメリットをみていきましょう。
同じ銘柄に投資するメリット
同じ銘柄に投資する場合、銘柄選定の手間がかからないのがメリットです。必然的につみたて投資枠の対象銘柄に絞って投資することになるため、個別株やETFなどに関して深く調べる必要性は低くなります。
また、成長投資枠の対象銘柄は非常に多いため、リスクの高い銘柄も含まれています。つみたて投資枠と同じ銘柄に投資することで、リスクの高い銘柄を避けられるのもメリットです。長期的に安定したリターンを狙える銘柄だけに投資できます。
投資初心者など、あまり知識がない方にとっては、2つの枠で同じ銘柄に投資するメリットは大きいといえます。
同じ銘柄に投資するデメリット
2つの枠で同じ銘柄に投資する場合、先述の通り、銘柄は必然的につみたて投資枠の対象に限定することになるため、多様なポートフォリオを構築しにくいのがデメリットです。堅実ではあるものの、投資に対して積極的な姿勢の方なら物足りないと感じてしまうかもしれません。
また、成長投資枠は個別株に投資できるため、上手く投資すれば市場全体のリターンより高いリターンを狙うことも可能です。また、個別株であれば株価の動きを見計らい指値注文もできます。
成長投資枠でつみたて投資枠と同じ銘柄を買う場合には、このような成長投資枠の特徴を活かせないため、もったいないと感じる方もいるでしょう。
つみたて投資枠で銘柄を選ぶ際のポイント

同じ銘柄を買う場合、つみたて投資枠では長期積立と分散投資を心がけることが重要です。ここでは、つみたて投資枠で購入する銘柄を選ぶ際のポイントをみていきましょう。
安定収益を生む銘柄を選ぶ
つみたて投資枠で購入する銘柄選びは、長期的にみて収益性の高い投資信託を選ぶのがポイントです。まずはトータルリターンを基準にして収益性が高いかどうかを判断するのも一つの手です。トータルリターンとは、分配金や値上がり益、ファンドにかかった費用などを含めて、一定期間でどれくらいの値上がり値下がりがあったかを示すものです。
長期的にトータルリターンの高い投資信託なら、過去の実績が安定しているという判断材料になるため安心して投資できます。また、純資産総額もみておくと良いでしょう。投資信託にどれくらいの運用規模があるかを見る指標にもなるため、一定水準以上の純資産総額の商品を選ぶことで、途中で償還になってしまう可能性を少なくすることができます。
投資信託は純資産総額が30億円未満になると、繰上償還が検討されるため最低でも100億円超の純資産総額のものを選ぶと安心です。
また、純資産総額をみる際には、規模と併せて推移にも着目してみましょう。純資産総額が増え続けているファンドは運用成績が伸びているか、もしくは人気が高いということになります。
長期投資・分散投資を目指す
つみたて投資枠は長期投資と分散投資を前提としているため、それに合った銘柄を選びましょう。インデックス投資信託なら、長期投資にも分散投資にも適しており、つみたて投資枠で購入する銘柄としておすすめです。
例えば、全世界型のバランス型投資信託なら1銘柄だけで全世界の地域に分散して投資できます。米国の代表的な500銘柄に分散投資できるS&P500連動型の投資信託も、つみたて投資枠で定番の銘柄です。
運用コストを確認する
投資信託を保有していると信託報酬という名目で運用コストがかかります。銘柄ごとに年間の信託報酬がパーセントで公表されているため確認しておきましょう。
例えば、信託報酬0.3%、商品を100万円分保有している場合には1年間で3,000円の運用コストがかかり、基準価額に毎日反映されています。長期間保有すると、それだけ運用コストの負担も積み上がっていくため、できるだけ運用コストの低い銘柄を選ぶのが得策です。
まとめ
NISAの成長投資枠でつみたて投資枠と同じ銘柄を買う場合には、銘柄選びで悩むことがなく手堅く投資できるのがメリットで、長期的に安定したリターンを狙えます。しかし、個別株やETFなどは買わないため、成長投資枠の特徴を十分に活かせません。したがって、市場全体のリターンよりさらに大きな利益は狙えないのがデメリットです。
メリットとデメリットをよく考慮した上で、同じ銘柄を買うかどうか決めるようにしましょう。
ご留意事項
免責事項
本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。