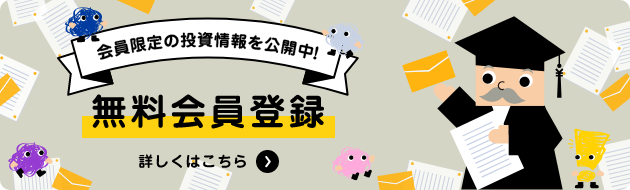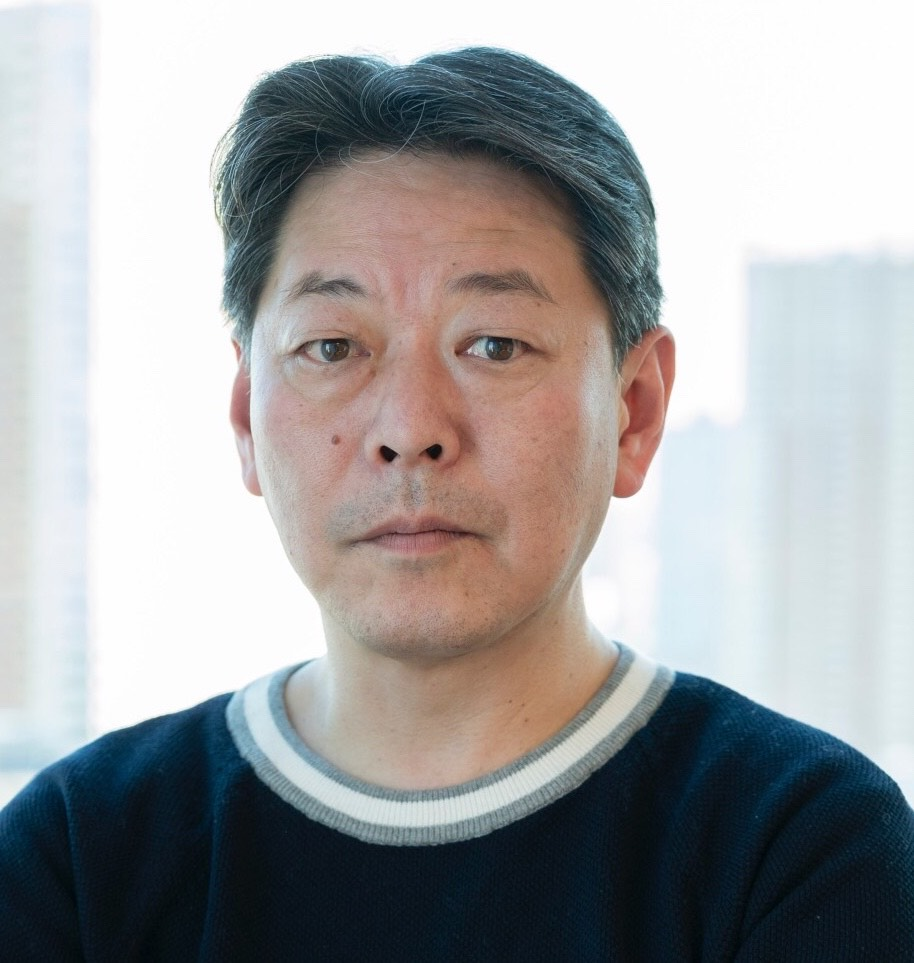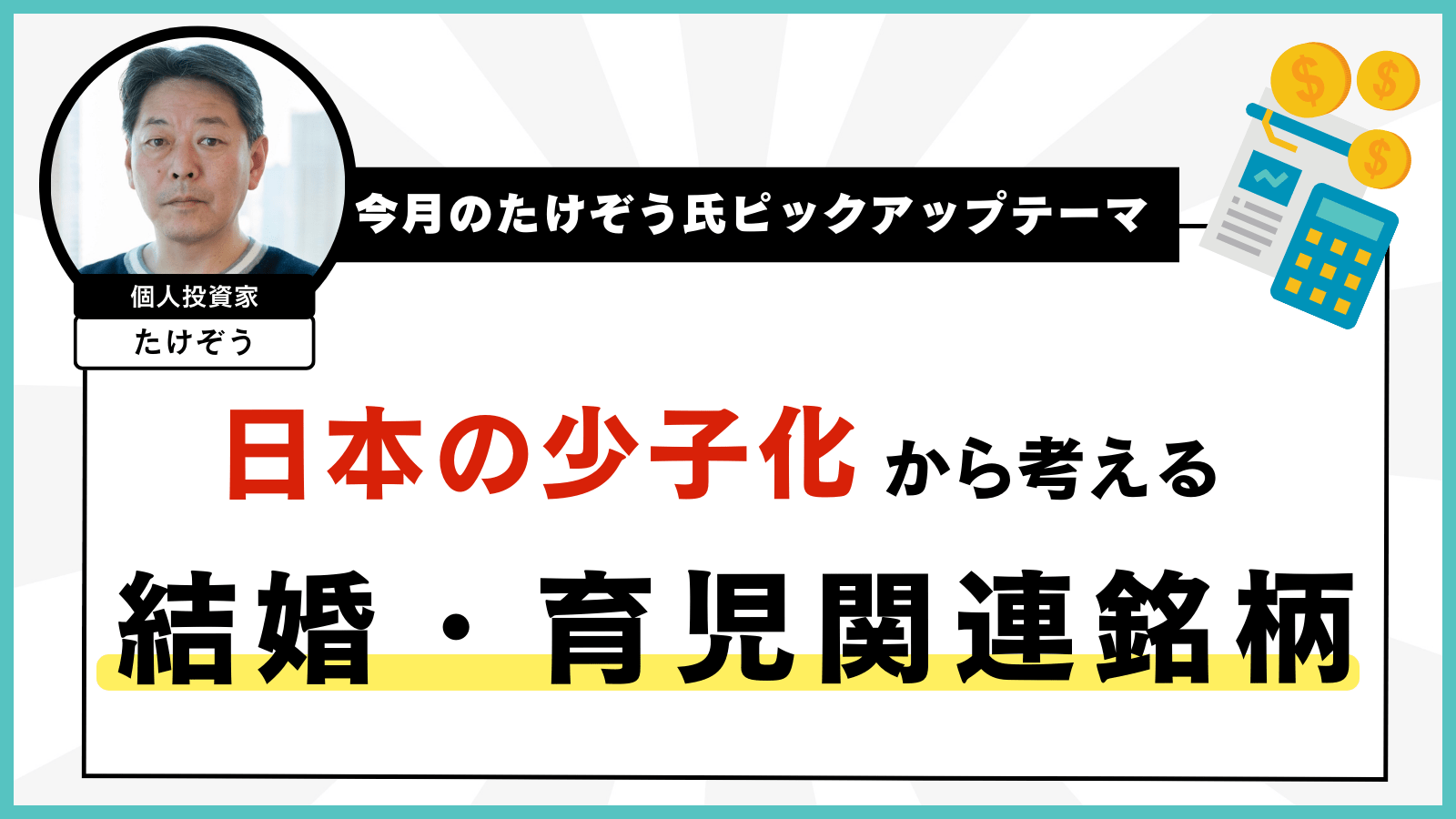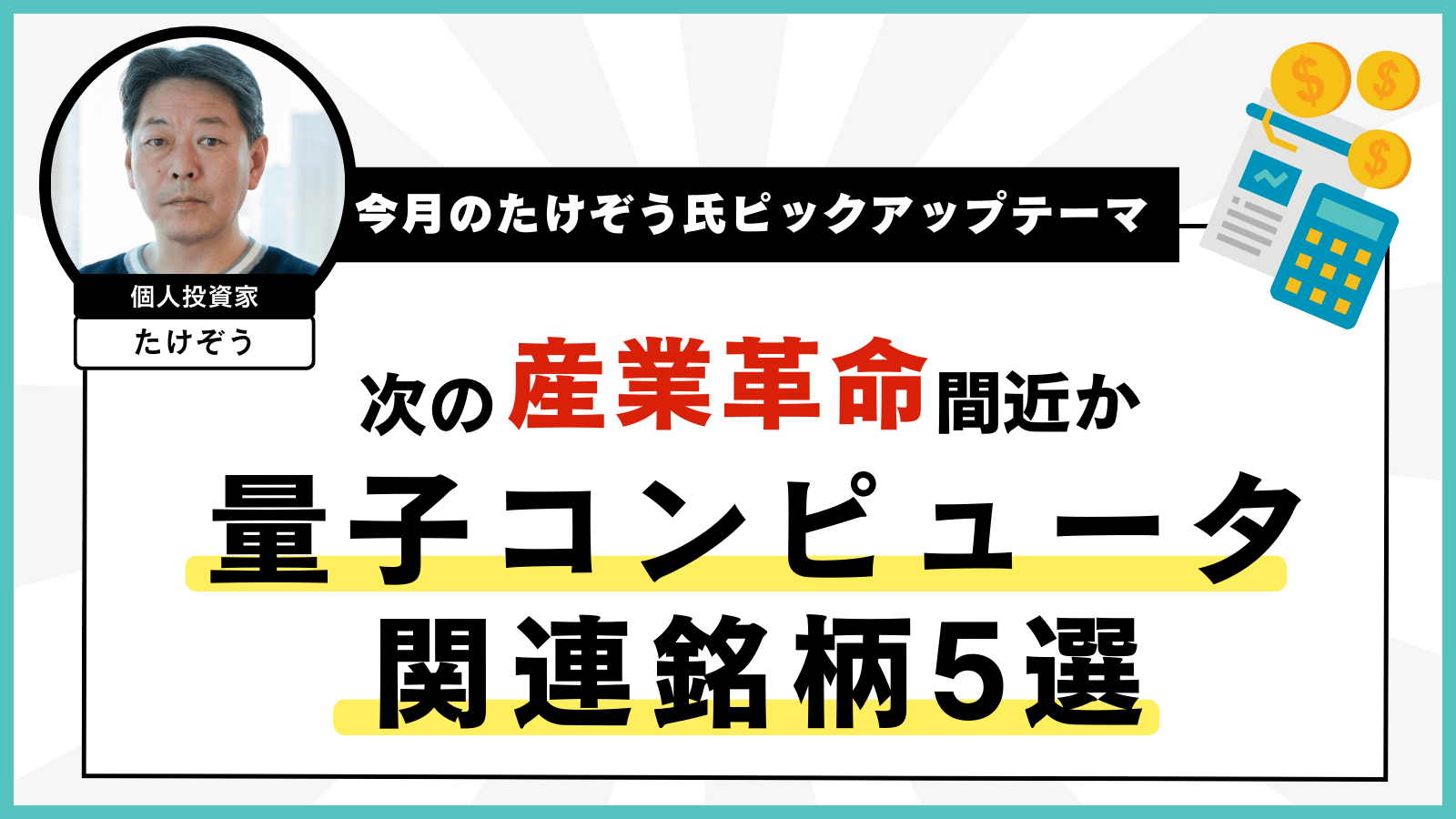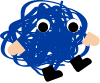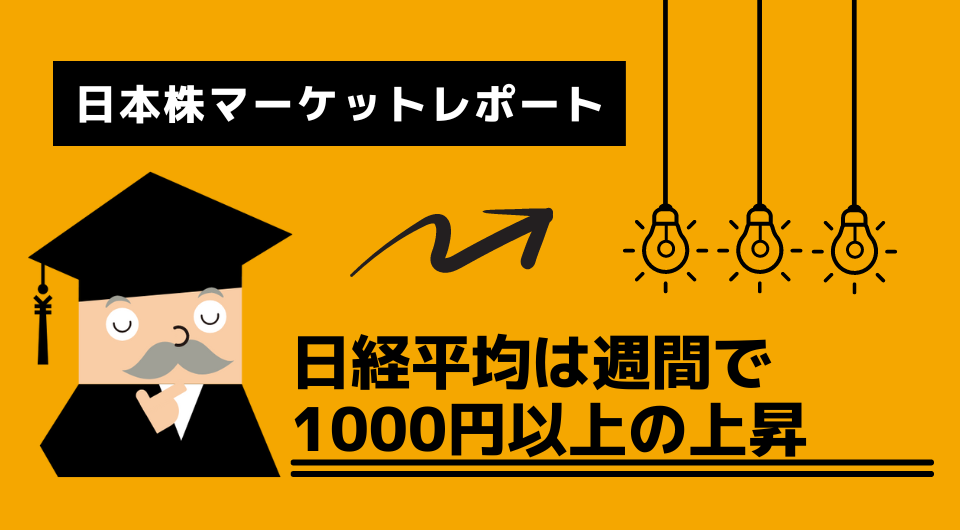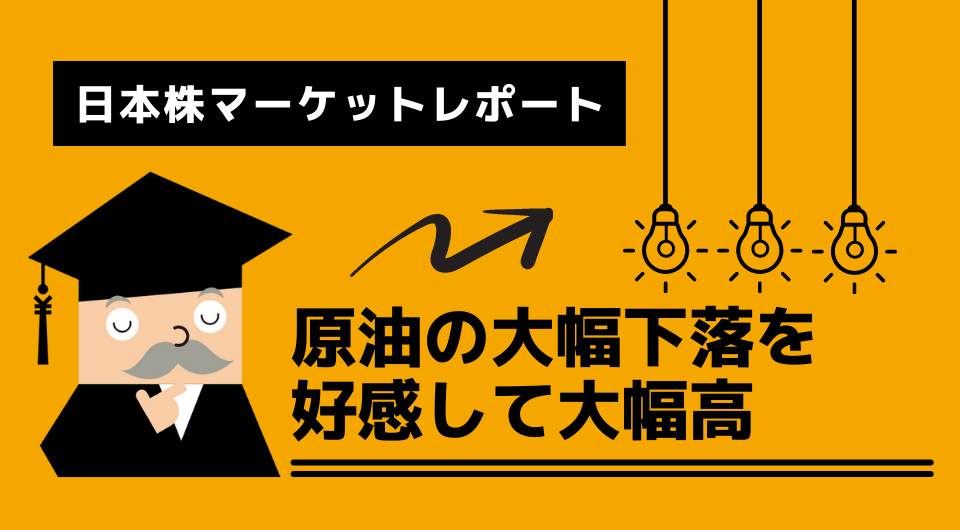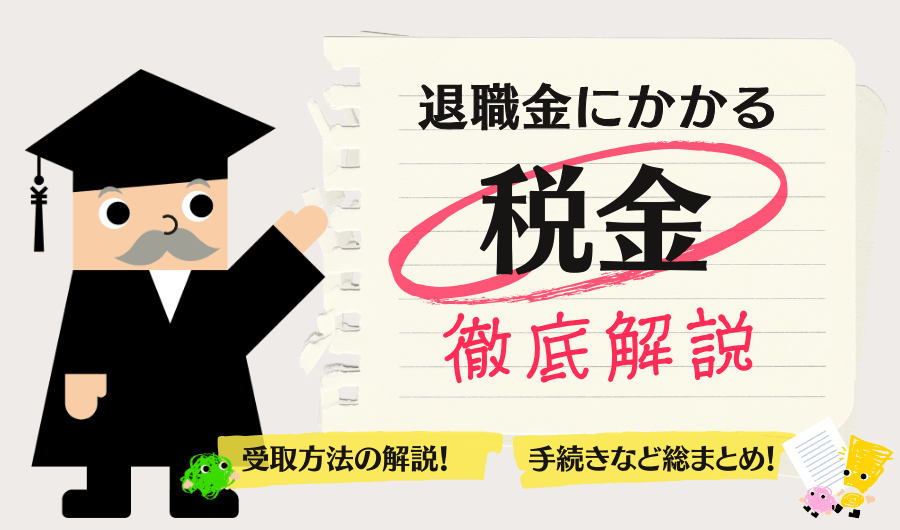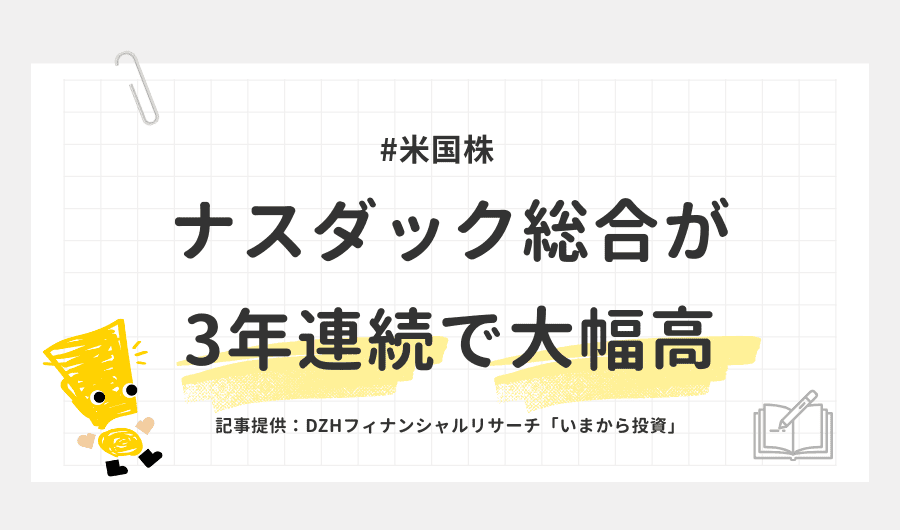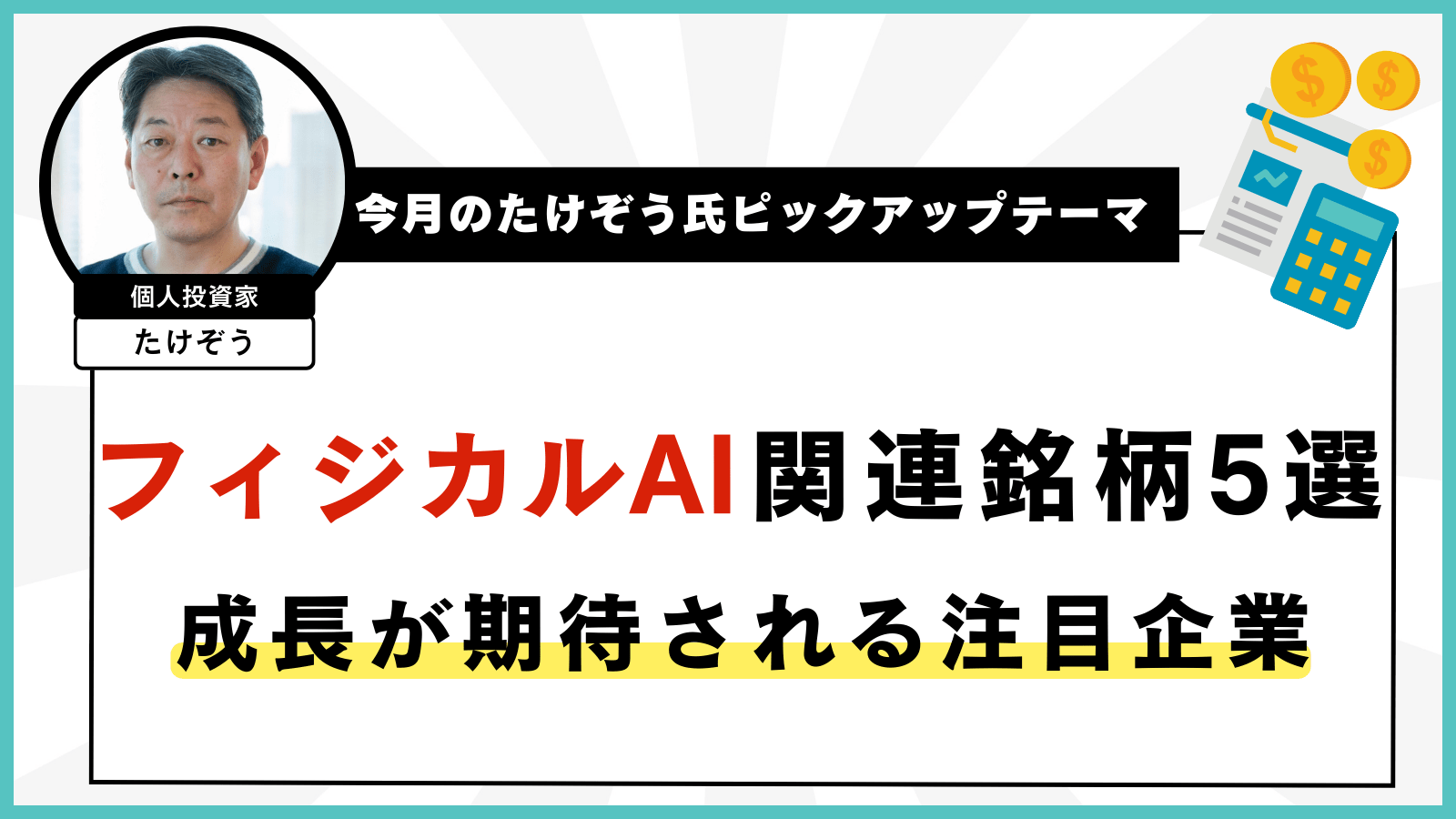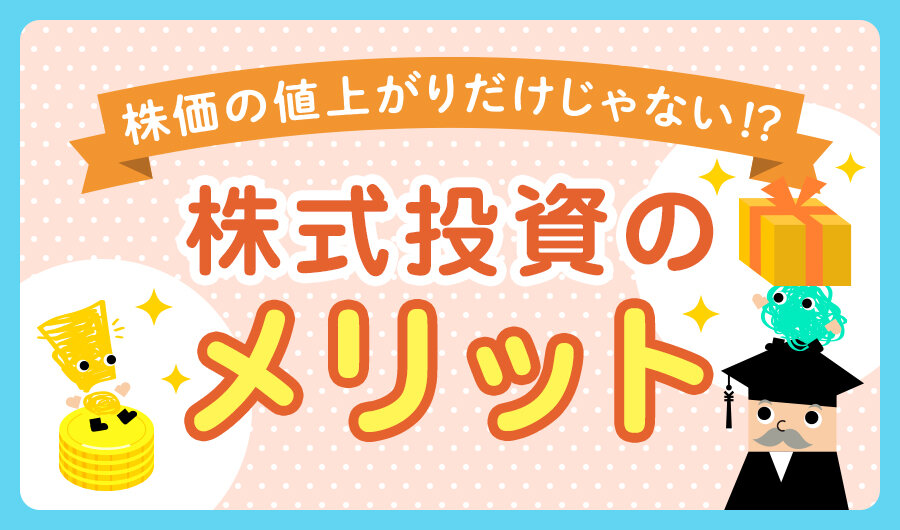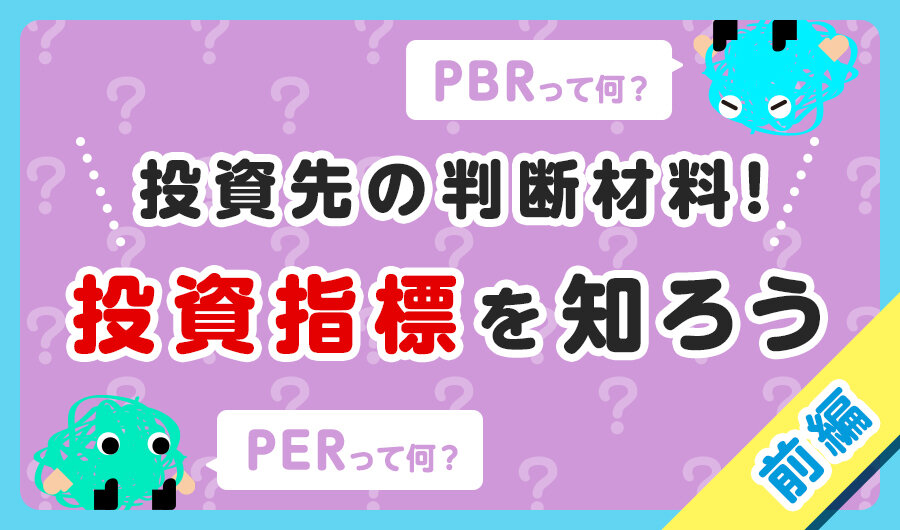【今月のたけぞう氏ピックアップテーマ】農業革命!食料安全保障と米価から考えるスマート農業銘柄5選
2025.06.26 (木)
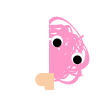
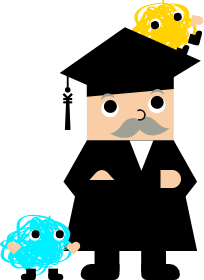

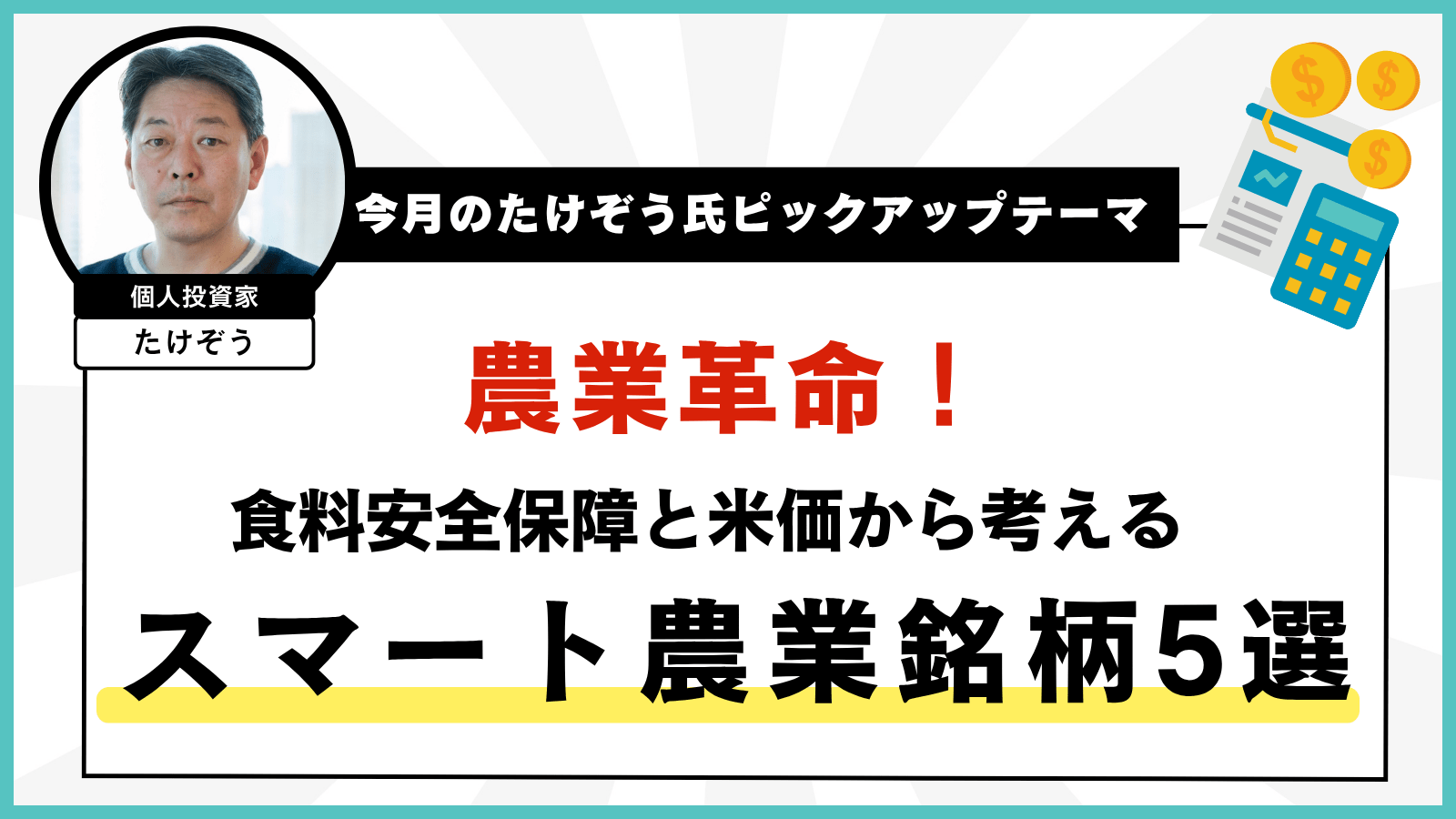
農業革命!食料安全保障と米価から考えるスマート農業銘柄5選
今年の話題の一つに米価格が上げられます。農林水産省が6月に公表した、業者の間で取引された5月のコメの相対取引価格は60キロあたり2万7,649円で過去最高値を更新しました。相対取引数量は5万2,000トンと5月としては最も少なかったことなどが影響しました。
しかし、卸売業者が銘柄米を日々取引しているスポット市場で、新潟県産コシヒカリなどの価格が直近のピークだった5月下旬から約3割下落しています。備蓄米放出の効果とみられています。
そうした中で、自民党の食料安全保障強化本部は、食料の安定的な確保に向け5年で2.5兆円規模の予算を求める決議書を政府に提出しました。通常の農林水産予算とは別枠で位置づける事を念頭に置いています。本部長の森山幹事長が石破首相と小泉農相にそれぞれ渡しました。概要としては、農地の大区画化やロボットを活用したスマート農業の導入などを支援すると示されています。そこで、今回はスマート農業の関連企業を取り上げます。
NEC(6701)
NEC(6701)は、電気機器製造業を営む企業です。同社の農業ICTソリューションはクラウドを活用することで点在する農場の一括管理やスピーディーな情報収集を可能とします。今年2月に最新の無線通信技術で農作業のデジタル化を支援する取り組みを始めるとしています。500メートル以上離れていても通信できるWi-Fiの新規格などを使い、農機やドローンを制御します。収益が低く、肉体的負荷が高いことによる後継者の減少など、農業が抱える大きな課題に取り組む姿勢を示しています。
クボタ(6326)
クボタ(6326)は、食料・水・環境の分野で事業を展開する大手総合機械メーカーです。特に農業機械や水インフラ関連の事業で知られています。同社は、2024年に、世界で初めて人が搭乗することなく自動運転で米や麦の収穫作業が行えるコンバインを市場投入し、トラクタ、コンバイン、田植機のすべてに無人運転仕様をラインアップしました。
また、2026年をめどに遠隔監視における無人運転農機を実用化するために、官学の研究機関とも連携して研究開発を進めています。食料需要の増加、農業人口の減少、カーボンニュートラルなど、食料分野においてさまざまな課題が立ちはだかる中で、同社の活躍場所は拡大傾向にあります。
井関農機(6310)
井関農機(6310)は、1926年創業の農業機械専業メーカーです。同社は6月12日に開いた新製品発表会でコストを抑えられる小型の乗用田植え機を打ち出しました。農業機械で日本国内の法人用途を開拓します。2030年までに同社売上高全体に占める大型農機の割合を、現在の40%から50%以上へと引き上げる目標を掲げています。また、同社は、他社より一足先に農地内の場所ごとの生育状況や土壌の状態に合わせて、肥料の量を調整する可変施肥技術に取り組んでおり、肥料の使用量を必要最小限に抑えながら収量を確保する営農体系を提案しています。
セラク(6199)
セラク(6199)は、ITソリューションを提供する企業で、特に農業分野においては、IT技術を活用した「みどりクラウド」というサービスを提供しています。農場環境を遠隔でモニタリングできる「みどりクラウド」を2015年から提供しています。みどりクラウドの提供によって、これまでに全国累計3000箇所を超える圃場の栽培環境を可視化し、栽培の安定化を実現しています。昨年11月に「みどりスイッチ」をリリースしました。それにより圃場内の設備を遠隔から操作することが可能となり、農業生産の省力化と生産性向上につなげる予定です。また「みどりクラウド らくらく出荷」は利益率の高いビジネスモデルであり、今後営業活動に注力すると説明しています。
オプティム(3694)
オプティム(3694)は、AI、IoT、クラウド、モバイル、ロボティクスを活用して、あらゆる産業のDXを推進する企業です。世界初のピンポイント農薬散布テクノロジーをはじめ、AI・IoT・Roboticsの活用により農業の省力化と高収益化に努めてきました。また、同社はスマート農業を活用し、栃木県栃木市、栃木県宇都宮市、茨城県高萩市の3地域でお米を生産しています。日本農業の持続可能な発展を実現することを目的に「オプティム・ファーム」を設立もしています。農業に非常に力を注いでいる企業です。
ご留意事項
免責事項
本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。