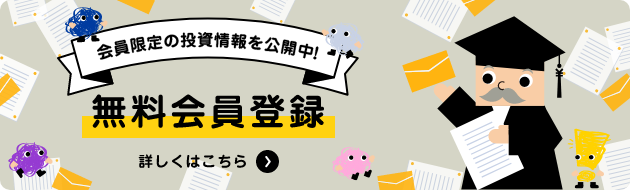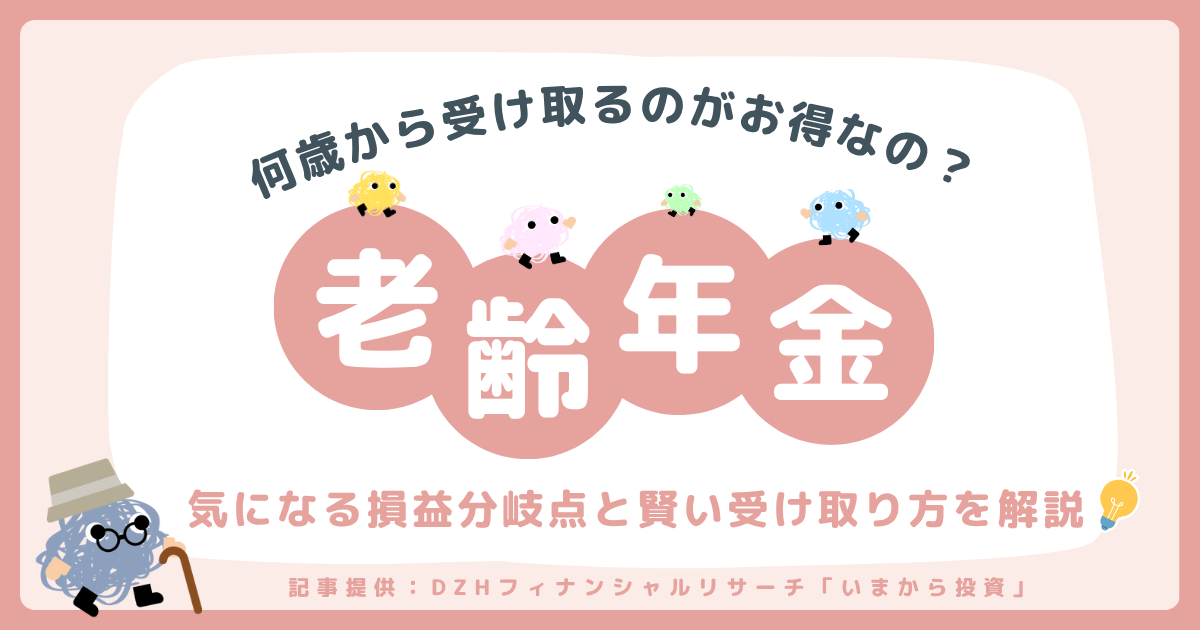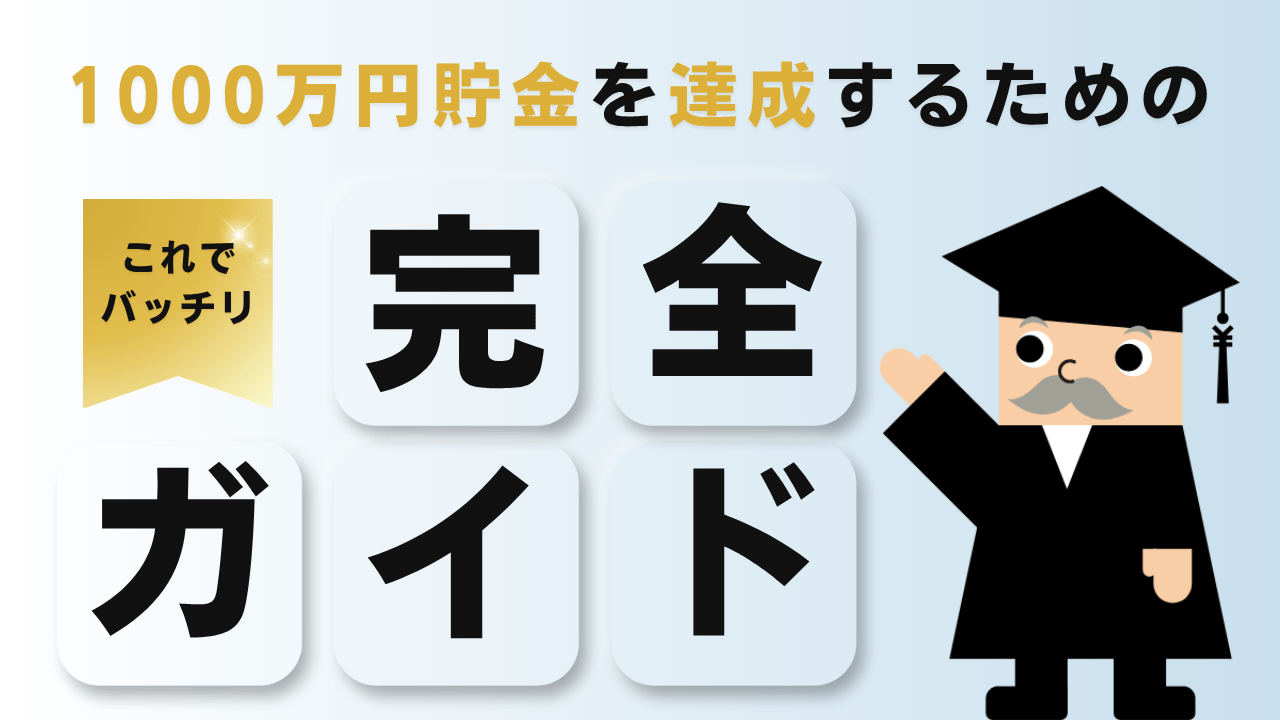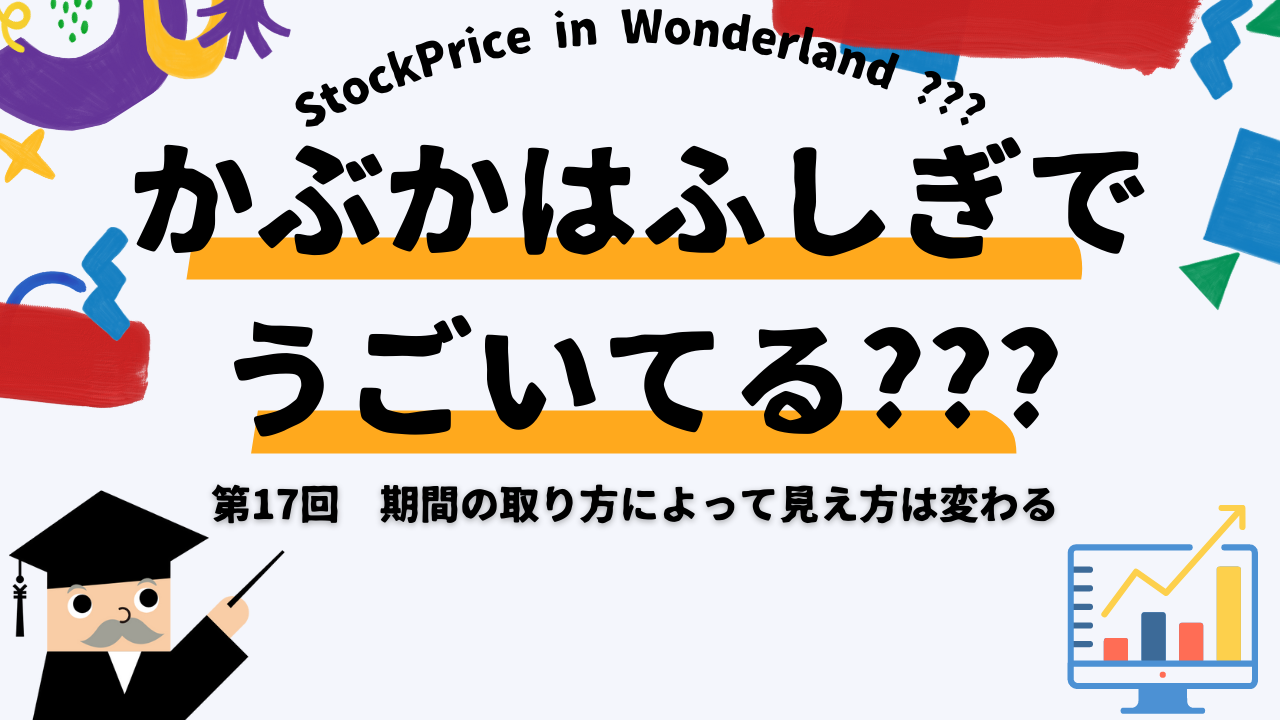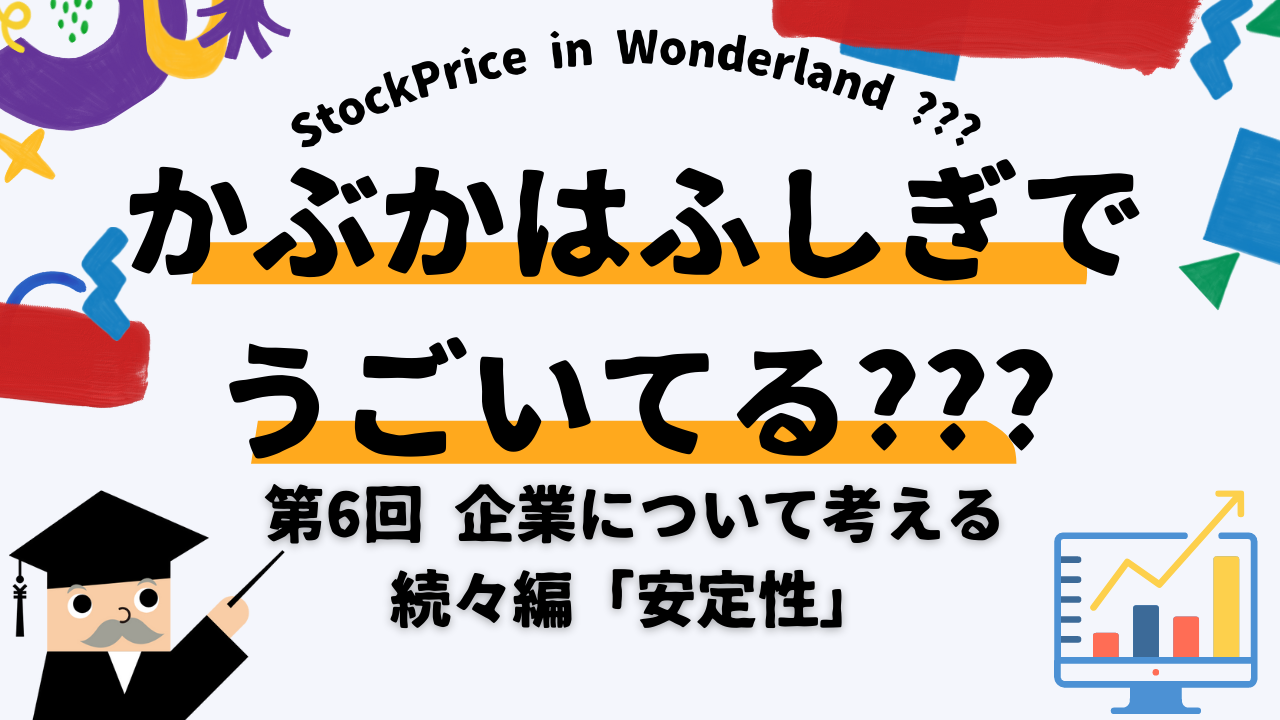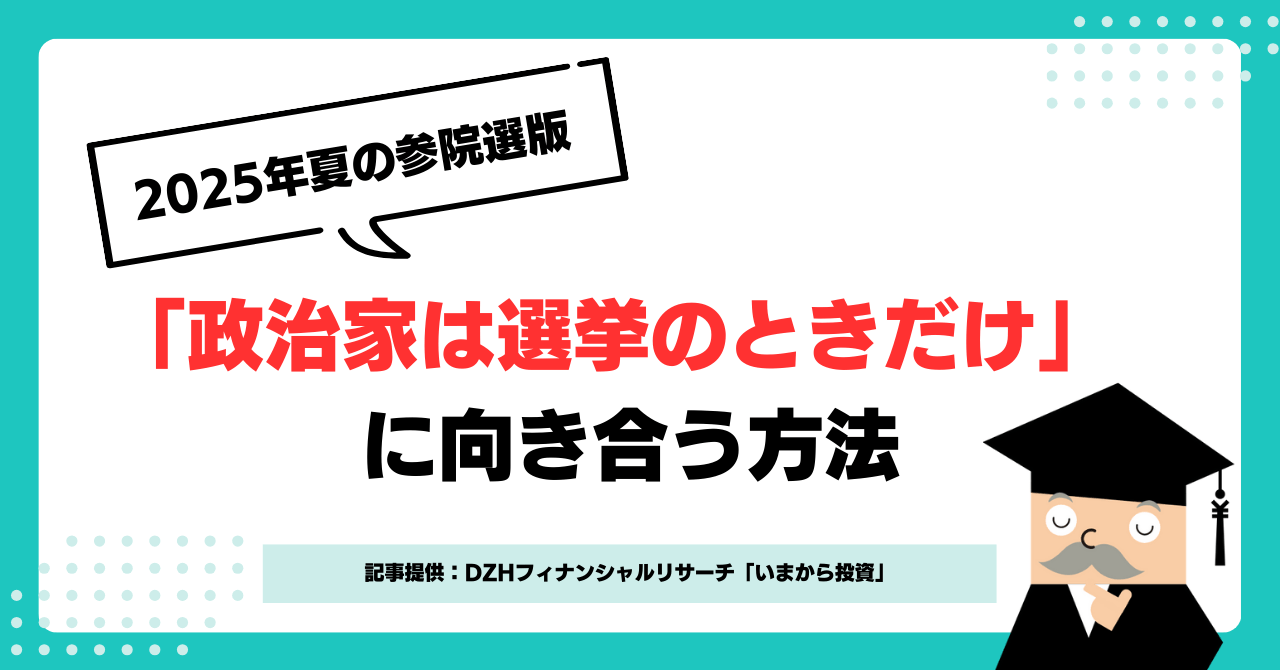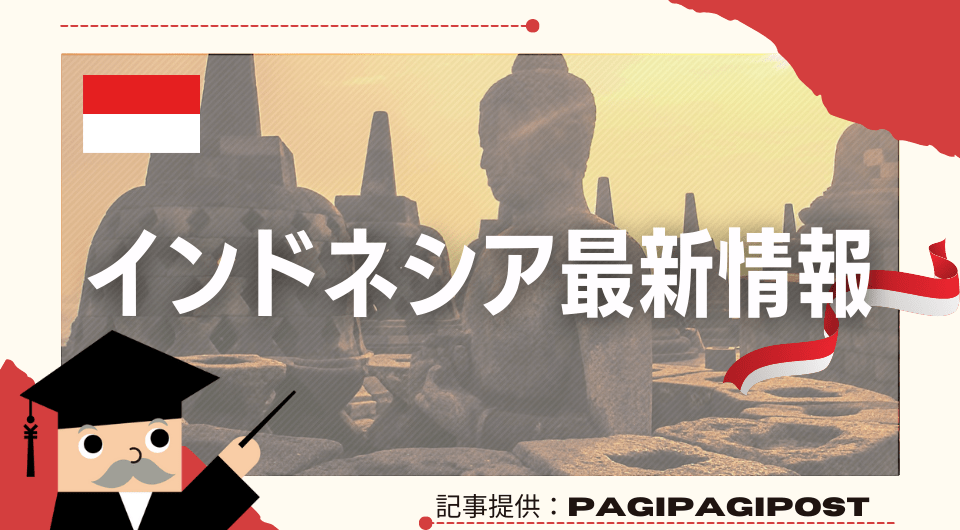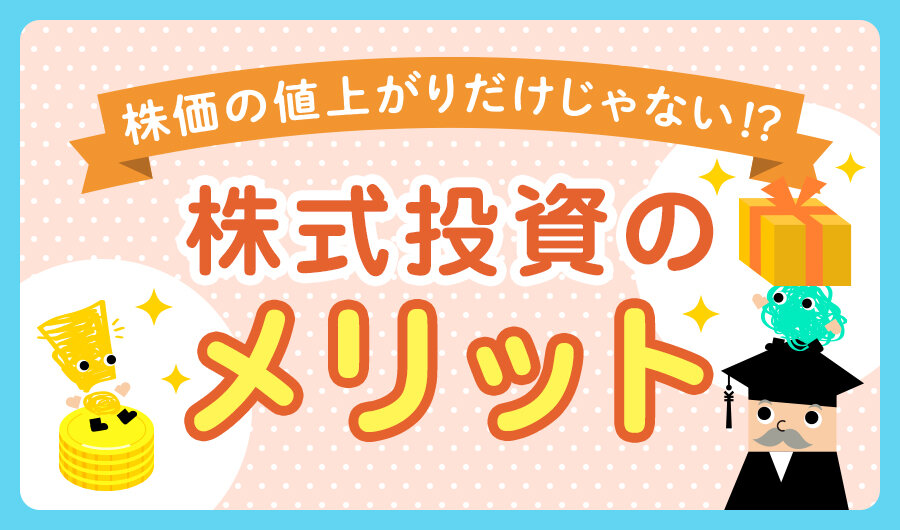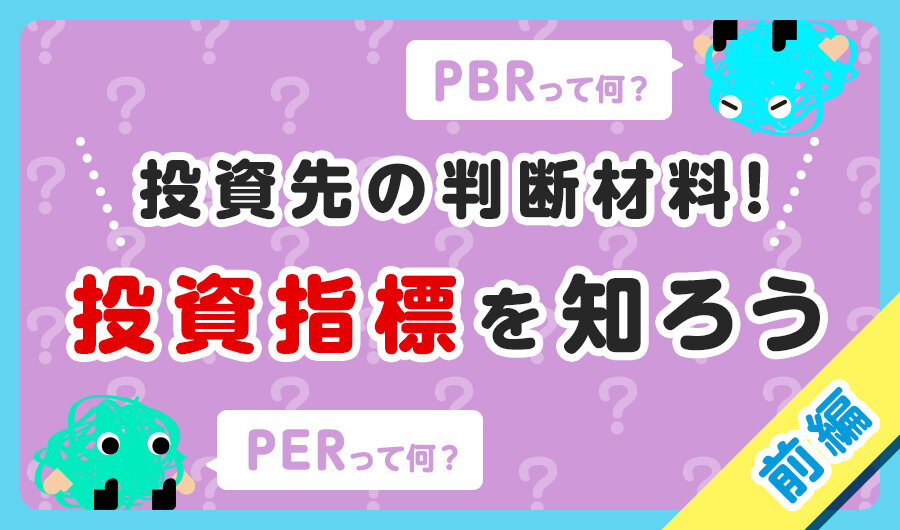計画・準備のポイントを紹介!老後資金の目安はいくら?
2025.07.11 (金)
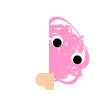
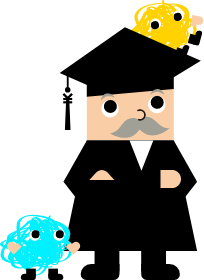

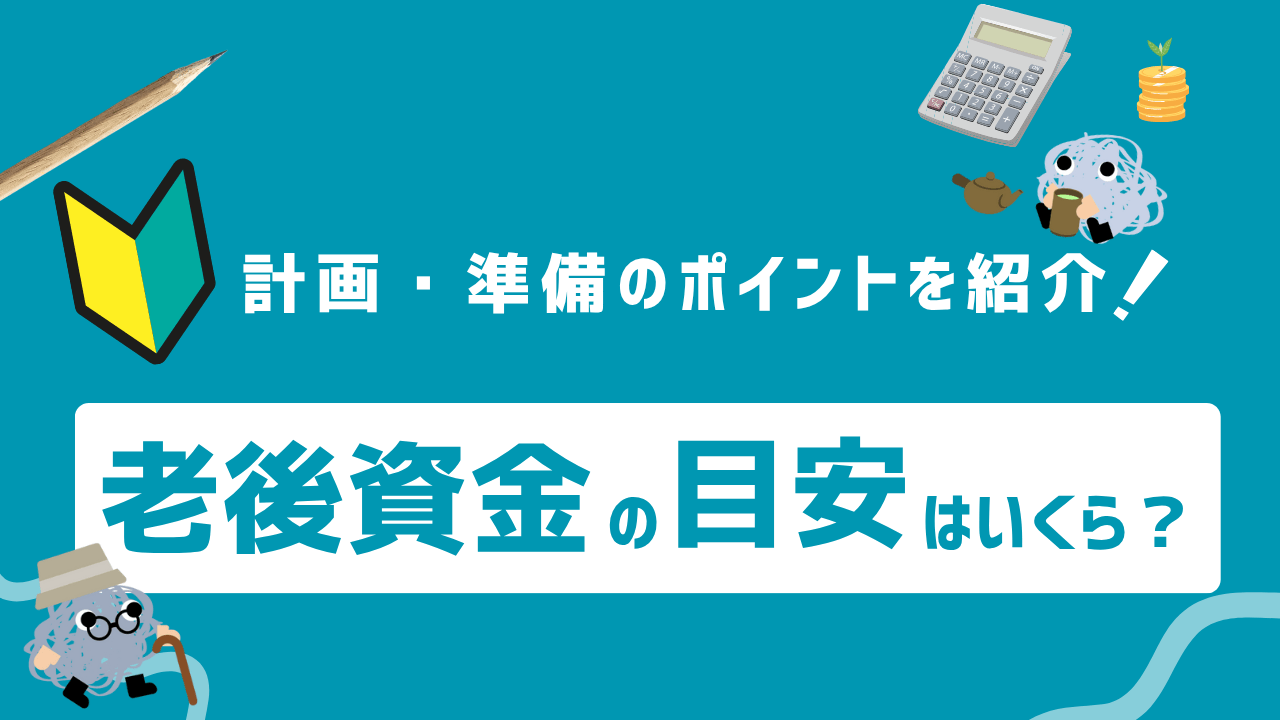
老後に向けた資金準備は、長寿化が進む日本でますます重要性を増しています。年齢を重ねてからの生活を充実させるためには、早めの計画と継続的な対策が不可欠です。
本記事では、老後資金の目安や最新の平均額、計算方法などを中心に、老後資金を確保するためのさまざまな方法を総合的に解説します。単身世帯と夫婦世帯で必要額が大きく変わってくる点や、具体的なシミュレーションの仕方にも触れていきます。
若いうちから自分に合った資産形成や働き方を意識することで、将来の不安を軽減できる可能性が高まります。正しい情報を押さえながら、老後に向けた計画をしっかり立てていきましょう。
一般的な老後資金と世間の実態
老後資金の必要額は個人や世帯構成によって大きく異なります。まずは、一般的な平均額や世間の実態をチェックしてみましょう。
日本では長寿化に伴い、老後の期間が20年以上にわたることも珍しくありません。夫婦二人で退職後に生活すると仮定した場合、統計上では1か月あたりの支出が十分なゆとりを持つならば30万円以上に上るとされるケースもあります。高齢者夫婦無職世帯の経済調査をみると、公的年金だけでは毎月赤字に陥る可能性が高いため、計画的に老後資金を蓄えていくことが良いでしょう。
さらに、総務省の調査によると、高齢の夫婦世帯では食費や光熱費だけでなく、医療費や介護費といった将来的な不安要素も増えてきます。こうした支出項目は年度によっても変動しやすく、インフレや健康状態の変化などによって出費が想定以上に膨らむリスクもあります。特に長生きリスクを意識して、余裕をもった資金計画が大切です。
単身世帯の場合も、生活費は夫婦世帯に比べて低い傾向にはありますが、家賃や光熱費などの固定費の負担を一人で担うために意外と費用がかさむことがあります。平均的な数値を鵜呑みにせず、自分の生活スタイルや健康状況、住まいなどを踏まえて必要な金額を考えることが重要です。
単身世帯と夫婦世帯で異なる必要額
老後資金の目安を考える上で、まず大きく変わるのが単身世帯か夫婦世帯かという点です。単身世帯の場合は、外食などの生活パターンが増えることによって家計のバランスが変化するほか、光熱費の割引が効きにくいなどのデメリットが生じる場合があります。一方で夫婦世帯では、食費などを二人で効率よく共有できる反面、大きな家に住み続けることが固定費の膨張につながることもあるため注意が必要です。

(参照元:家計調査報告〈家計収支編〉2024年〈令和6年〉平均結果の概要 丨総務省統計局)
生活費の観点からは、月々で単身世帯であれば約16万円、夫婦世帯であれば約28万円といった支出例が示される調査結果もあります。ただし、これらの数値は平均的なものなので、実際には余裕をもった設定をしておくほうが安心です。結婚や家族構成の変化に合わせて定期的に再計算を行い、最新の状況を踏まえた資金計画を作り直すことが大切になります。
さらに長寿化を踏まえた場合、多くの方が20年から30年近い老後生活を送る可能性があります。毎月の不足分を年間に換算し、それを複数年積み上げると1000万円単位で想定を上回る金額となることもあるため、早めの対策が老後の安心につながります。
ゆとりある老後と最低限の生活費の違い
老後資金の目安を考えるうえでは、どの程度の暮らしを送りたいかというライフスタイルの違いも大きな影響を及ぼします。最低限の生活費だけを確保できればよいと考えるか、趣味やレジャー、旅行を楽しむ余裕を持ちたいかによって必要な金額に大きな差が生まれます。具体的には、ゆとりある老後なら毎月35万円以上は必要という統計もあるため、現役時代と同等の出費を想定するならばより多くの蓄えが要ります。
加えて、家族や友人との付き合い方や将来における介護負担の度合いでも資金計画は変わります。たとえば、まとまった費用がかかる介護施設への入居を検討しているのであれば、数百万円単位での初期費用が必要となるケースもあるのです。可能な限り先を見据えて備えることが、経済的にも精神的にも安心感につながります。
また、住む土地の医療体制や交通インフラによっても必要資金が異なる点を忘れてはいけません。地方に住む方は車の維持費がかさむ可能性がある一方で、都市部は住宅費や食費が高くつく傾向にあります。こうした立地要因も含め、自分に合ったゆとりある老後を描くことが重要です。
年金・退職金を活用した老後資金対策
老後資金の柱となる公的年金や企業年金、退職金などをうまく活用することで、資金不足を補い安定した生活を目指すことが可能です。
日本の老後資金を支える主な収入源には、公的年金と企業年金・退職金があります。公的年金の基本的な仕組みを理解すると、自分がどのタイミングでどれぐらいの年金を受け取れるかが明確になります。これらの制度は多くの場合、終身で給付が続くため、長生きリスクに対して重要な役割を果たすのが特徴です。
また、企業によっては独自の企業年金制度を設けていることもあり、退職時に一括で支給される退職金とあわせて、老後の収入源をより強固に支える仕組みがある場合があります。退職金は比較的大きな金額が手に入る一方、活用方法によっては運用益を狙える可能性もあり、受け取った後も継続して資産運用を行うと老後資金を効率よく増やせるかもしれません。
ただし、年々変化する社会情勢や法改正によって制度内容が変わることがあるため、退職時期を早めるか、それとも定年延長や継続雇用の制度を利用するかなど、こまめに情報をチェックして判断する必要があります。企業年金や退職金の額をしっかり把握することで、老後に必要な貯蓄とのバランスをとりやすくなるでしょう。
公的年金の受給額を把握しよう
公的年金は老後資金の基礎となる収入源です。国民年金や厚生年金など、自分がどの制度に加入しているかによって受給額は異なります。国民年金のみの場合は月額6万円程度(満額の場合)が目安とされることが多く、一方で厚生年金を受給できる方は支給額が大きくなりやすいという特徴があります。
公的年金の仕組みを把握するうえで役立つのが、年金定期便や年金ネットです。自身のこれまでの納付実績や見込み受給額をチェックすることで、将来の生活設計を具体的にイメージしやすくなります。特に、受給開始年齢を65歳よりも繰り下げることで月々の受給額が増える仕組みもあり、一人ひとりのライフプランや健康状態を踏まえて検討することが大切です。
ただし、年金制度そのものも見直しが進み、受給開始年齢を繰り下げても期待ほど増額が得られないことや、法改正によって条件が変わる可能性がある点には注意しましょう。事前に可能性やリスクを考慮して、老後資金に不測の事態が起きないよう余裕を持たせた計画が必要です。
企業年金・退職金と公的年金の組み合わせ
多くの企業では定年退職時に退職金が支給される仕組みがありますが、その金額は企業の業績や勤続年数、個人の役職などに左右されます。退職金がある程度まとまった額になる場合には、公的年金とあわせて老後の主要な収入源になることが期待できます。
企業年金は公的年金を補完する仕組みとして、確定拠出年金(企業型DC)や確定給付年金などが整備されていることが多いです。会社ごとに制度が異なるため、在職中から自社の年金制度の内容を確認しておくことが重要です。そのうえで、退職後の資金繰りにどのように組み込むべきかを分析すると、老後に必要な貯金計画を立てやすくなります。
公的年金と企業年金、退職金を合わせた合計額がどの程度の生活水準を支えてくれるかを早い段階で見極め、もし不足が予想されるならばNISAやiDeCoなどの自助努力によって補完する方法を検討するとよいでしょう。
NISA・iDeCoで資産形成を効率化する
税制優遇があるNISAやiDeCoを活用すれば、長期的な資産形成の効率が高まります。老後資金を増やすための基礎知識として押さえましょう。
公的年金や企業年金に加えて、自助努力として重要視されるのが投資による資産形成です。長期間の積立投資は、複利効果によって時間をかけて資産が増える可能性が高まります。特にNISAやiDeCoのように税制上のメリットが用意されている制度を活用すれば、運用益が非課税になるなどの恩恵を受けやすく、老後資金形成には最適な選択のひとつと言えます。
投資にはリスクがつきものですが、分散投資や運用コストを抑える工夫を行えば、リスクを緩和することも可能です。長期で見ると株式や投資信託などのリスク資産でも、一定のリターンが期待できる傾向にあります。自分のリスク許容度と照らし合わせながら、早めに少額から始めることが、結果的には老後資金を増やす近道になりやすいでしょう。
ただし、NISAやiDeCoには制度ごとの年齢制限や掛金上限、運用商品ラインアップの違いなど、細かいルールがあります。これらを理解していないと、十分な効果を得られなかったり、予定よりも資産が増えないという結果につながる可能性もあるため、事前の情報収集が大切です。
NISAの種類と活用メリット
NISAには成長投資枠とつみたて投資枠の2種類があり、それぞれ非課税投資枠や投資期間が異なります。成長投資枠は幅広い投資商品に対応しており、年間投資上限額が大きいのが特徴です。一方でつみたて投資枠は、低コストな投資信託などが対象商品となり、長期投資を支援する仕組みとなっています。老後資金の目安を達成するための長期運用には、つみたて投資枠を活用する人も増えています。
投資から得られる配当や売却益が非課税になることは、資産の成長を加速させるうえで大きなメリットです。特に複利の効果を長期間にわたって享受できるため、若いうちに始めるとより恩恵が大きくなります。投資対象の商品リスクを分散させながらコツコツ積み立てれば、仮に市場が一時的に下落しても、時間をかけてリカバリーしやすいところが強みです。
ただし、NISAはあくまで運用の成果が見込める商品を選ぶ必要があるため、何に投資するかは慎重に検討しましょう。プロに相談したり、投資関連の情報を定期的に追いかけたりして、リスクを極力下げる努力をすることが望ましいでしょう。
iDeCoを始める際の仕組みと注意点
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金を拠出して自分で運用商品を選び、その成果によって将来受け取る年金額が変わる仕組みです。掛金が全額所得控除の対象となり、運用益も基本的には非課税であることなど、節税効果が非常に高い制度として注目されています。
ただし、職業や加入している年金制度によって掛金の上限が異なる点には留意が必要です。また、原則として60歳まで途中換金できないため、流動性が低いというデメリットがあります。短期的に資金が必要になる可能性がある場合は、預貯金など他の手段を確保しておくことが安全策となります。
iDeCoを始める前には、制度の詳細や手数料、運用コストなどをしっかり把握し、自分に合った金融機関と商品を選ぶことが肝心です。掛金を毎月コツコツと積み立てることで、将来の老後資金を着実に増やす道につなげていきましょう。
老後資金を増やすための働き方と節税策
60歳以降も働き続けることで、老後資金を補填するだけでなく、生きがいや社会参加の機会も得られます。節税面での工夫も検討しましょう。
定年退職や早期退職を迎えても、人生はまだまだ続きます。再就職や副業、起業といった形で働き続けると、収入を得られるだけでなく、社会とのつながりを保ちながら健康的な日常を送れる利点もあります。特に近年はシニア人材の需要が比較的高まっており、経験やスキルを生かした働き方がしやすくなっています。
また、働き続けることによって年金の受給時期を繰り下げれば、年金額を増やすことも可能です。この繰り下げ受給の仕組みをうまく活用すると、長い目で見て年金収入が増えるだけでなく、自分のライフスタイルに合わせて退職の時期を選べます。ただし、健康状態や家族の状況なども踏まえる必要があるため、単純に金額だけではなく総合的な判断が必要です。
さらに、副業や起業による収入は個人事業主扱いとなり、確定申告で経費を計上することで節税につなげられるケースもあります。適切に経費を活用すれば、手取り額を増やしながら老後資金を補強できるかもしれません。状況に応じて社労士や税理士などの専門家に相談し、効率的な働き方を検討することが大切です。
まとめ:早めの準備で安心の老後を迎える
老後資金を十分に確保するためには、若いうちからの計画的な取り組みが欠かせません。今回紹介したポイントを踏まえ、将来に向けたライフプランを考えてみましょう。
老後資金の目安は、単身世帯か夫婦世帯か、あるいはゆとりを重視するか最低限の生活を重視するかによって大きく変わります。平均統計を参考にしながらも、自分自身のライフスタイルや健康状態、家族構成などに合わせて、具体的なシミュレーションを行うことが重要です。
公的年金をはじめ、企業年金や退職金、NISAやiDeCoなどの資産形成制度を組み合わせれば、老後の収入を安定させたり上乗せしたりすることが可能です。特に、税制優遇を活かした長期運用や、働き続けることで年金の繰下げ受給を検討する方法など、柔軟な選択肢が広がっています。
将来に余裕のある老後を迎えるためには、できるだけ早いうちから対策を始めることが大切です。少額でもコツコツと積み立てを続けながら、ライフイベントに合わせて計画を見直し、老後資金不足のリスクを最小限に抑えていくことが、安心して歳を重ねるための第一歩となるでしょう。
ご留意事項
免責事項
本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。